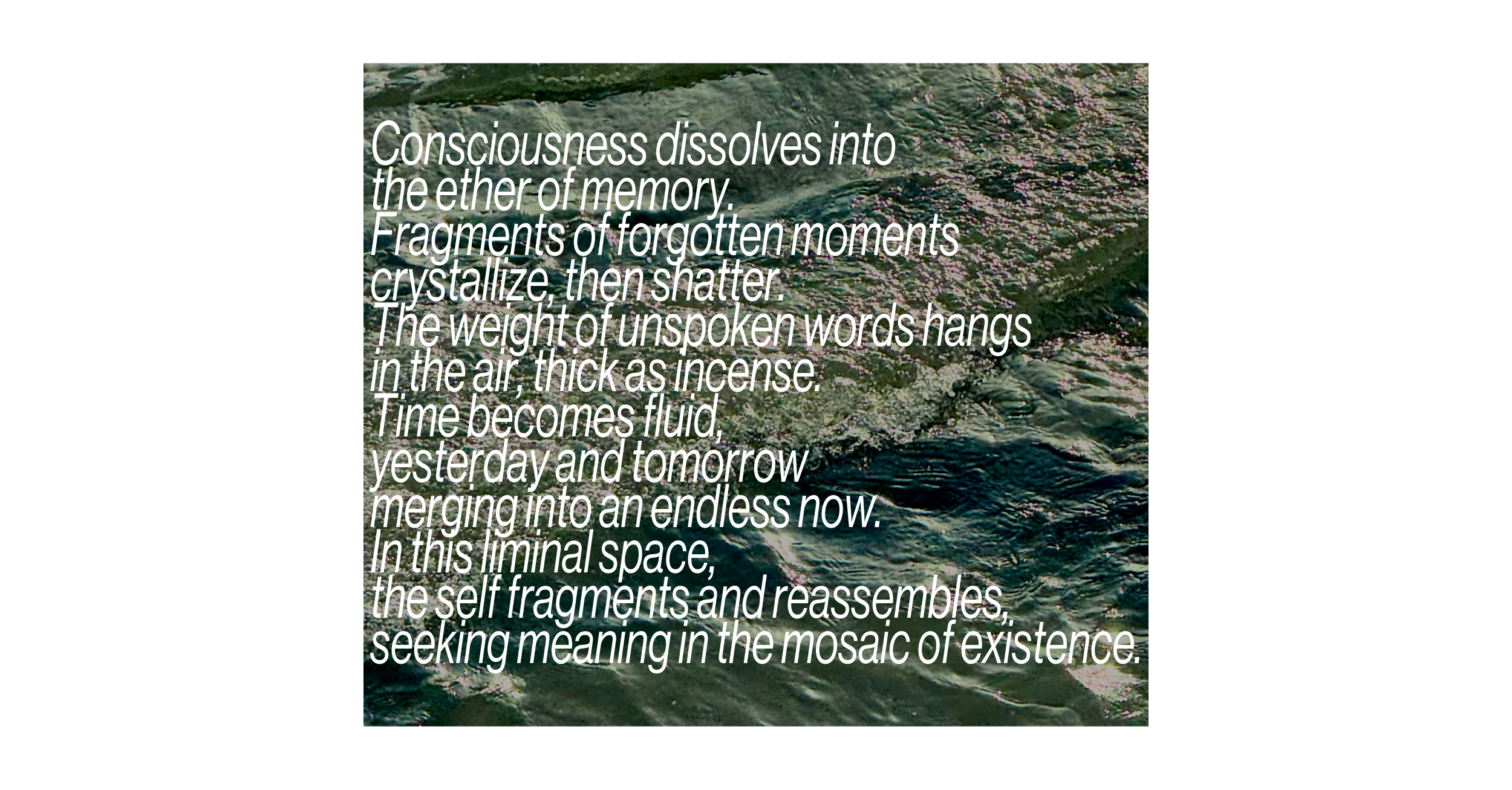1週間と3日経って、ようやく「来週はうちに帰ってきなよ」とメッセージを送った。
君の帰る場所がほかにあるかどうか、僕は知らない。君が自分から電話をかけて来たのはたったの一度だけ、午前2時ごろだったのを覚えている。
泣いているのに「ごめん、間違えたみたい。」と言って電話は切れた。僕は深追い出来る立場じゃなかった。
トモダチが普通どこまで踏み込むのか、ちっとも分からなくてどうしようもなく胸が痛かった。結局そのまでの信頼関係だった、と思い知らされたことも痛みの一因だったかもしれない。
他に甘える男がいるのかもしれない、そう浮かんだ。だから僕は、君のくちびるを奪うのをやめた。
その代わりにたぶん少しだけ、しつこい男になったと思う。
きみが煙草をうちに持ってきた時も、せめて隣にいる時は自分の匂いでいて欲しいと思ってそれを奪った。そして彼女が宵のこの表情を許すのは自分だけであれと、そう願った。
「願うだけで、叶えば良いのに。」
独り言は夏の湿り気に混じって、昼の強すぎる日差しと共にジト、とした汗に滲む。
もし君と出会わない人生があったとしても、自分はそれを選べないだろう。
自分が浅ましくてバカらしくて、可笑しくって笑える。
なのに苦しいのは君のせいだ。
それなのに愛おしくて大事で堪らない。
いつか昼間のまどろみも、君のとなりで過ごしたい。