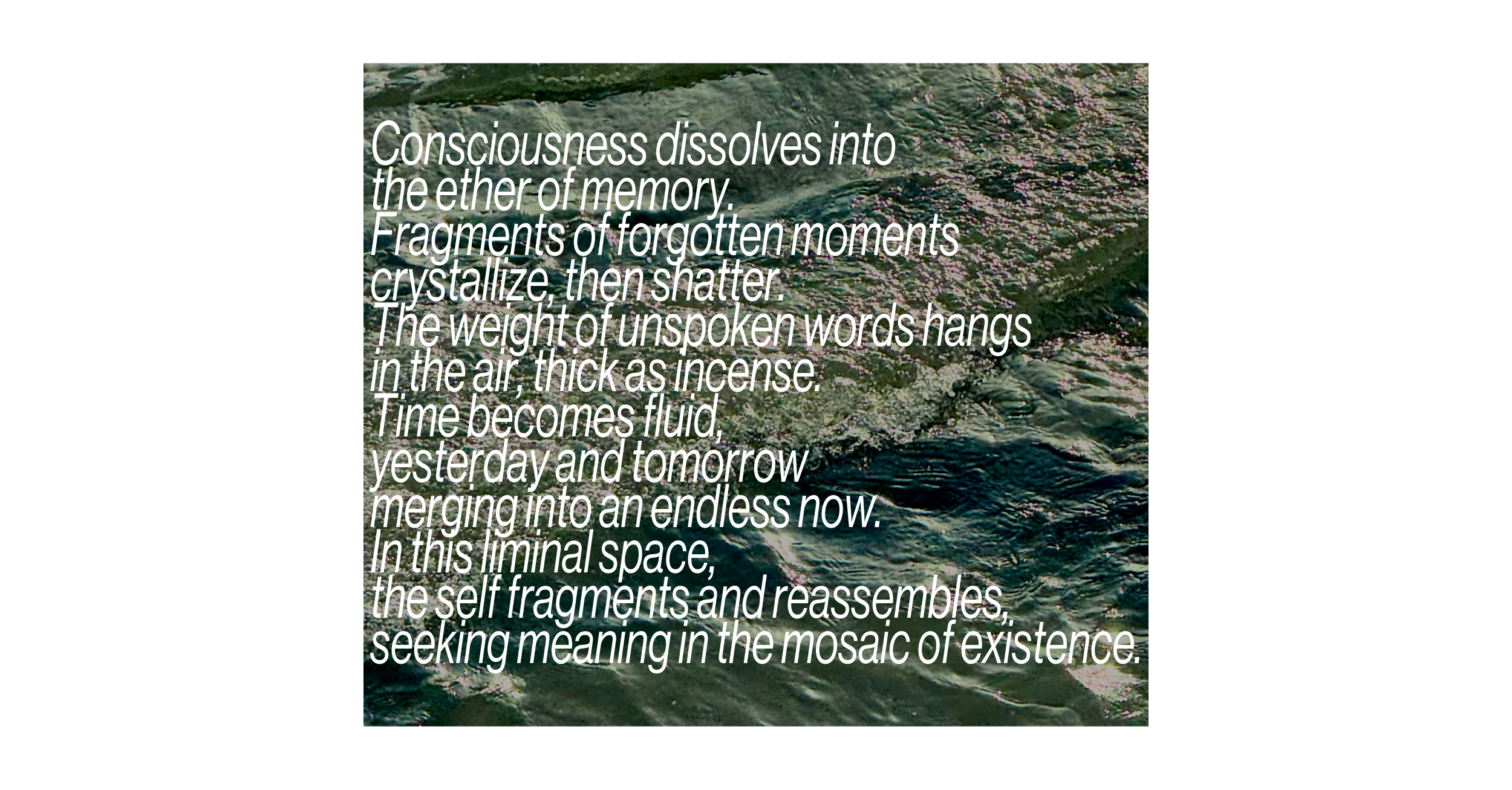駅の改札口は人で溢れかえっていた。これから家に帰る人、飲みに出る人、誰かと待ち合わせをしているのか駅の柱にもたれ掛かる人。
2週間ぶりに訪れた場所の景色は全く変わっていないように見えて少しずつ季節を移ろわせている。いつもの街じゃ気付かない変化も、違う街でなら気付けるものだ。街路樹の緑は青さを増して、道端に咲いた紫陽花は色を失いかけている。
傷んできたパンプスの踵を鳴らしながら、すっかり覚えてしまった道を辿った。短いような長いような、駅から徒歩12分のマンションに着く。
「あ。」
男の部屋の番号は何度訪ねても覚えられなかった。今日も何処かに残したはずのメモを探していたら、コンビニの袋に伸びたTシャツ姿の男と出くわした。
「おかえり。」
「買い物?」
ただいま、とは答えられない。だってここは私の家じゃない。誤魔化すように適当に話題を振った。
「ああ、暑いしアイスでもどうかなと思って。」
「何味?」
「クッキー。名前好きでしょ。」
ああ、どうしてそうして私を甘やかすの。
「遅かったけど、仕事?」
「うん、残業。」
「そっか、お疲れ。暑いから早く上がりなよ。アイス溶けるし。」
私の肩を引き寄せて頭を撫でる彼の手を払う事は出来なかった。ああ、この人はこうして人に触れるのだ。空いた時間で忘れることが出来かけていた筈なのに、触れあった手と手の温度が、全てをありありと思い出させる。
心が、溶けそうだ。こんなに幸せなのに、私たち2人はにせものだ。
エレベーターを待つ間に見あげた男の、下がった目尻にどんな意味があるのか、私には分からなかった。
乗り込んだ籠の中で交わされる空虚な会話はたわいも無い、それなのに私に慮った柔らかな言葉だけで流れていく。
優しすぎる人だ、ずっと。
ここなら赦される気がして、神様に見えていない気がして、指を絡めた男の肩に頭を預ける。ごめんなさい、と言う何処に向けたか分からない懺悔の詞が浮かんだ。
「寂しかった?」
「……分かんないや。」
「そこは嘘でも寂しかったって言えよ。」
そうやって笑ってくれる彼の強さがありがたかった。
家の前まで手を引かれる私の姿は、他人から見たら彼の恋人に見えているのだろうか。
肌に張り付いたシャツを思い、鍵の開いた音を聞きながらそう思った。