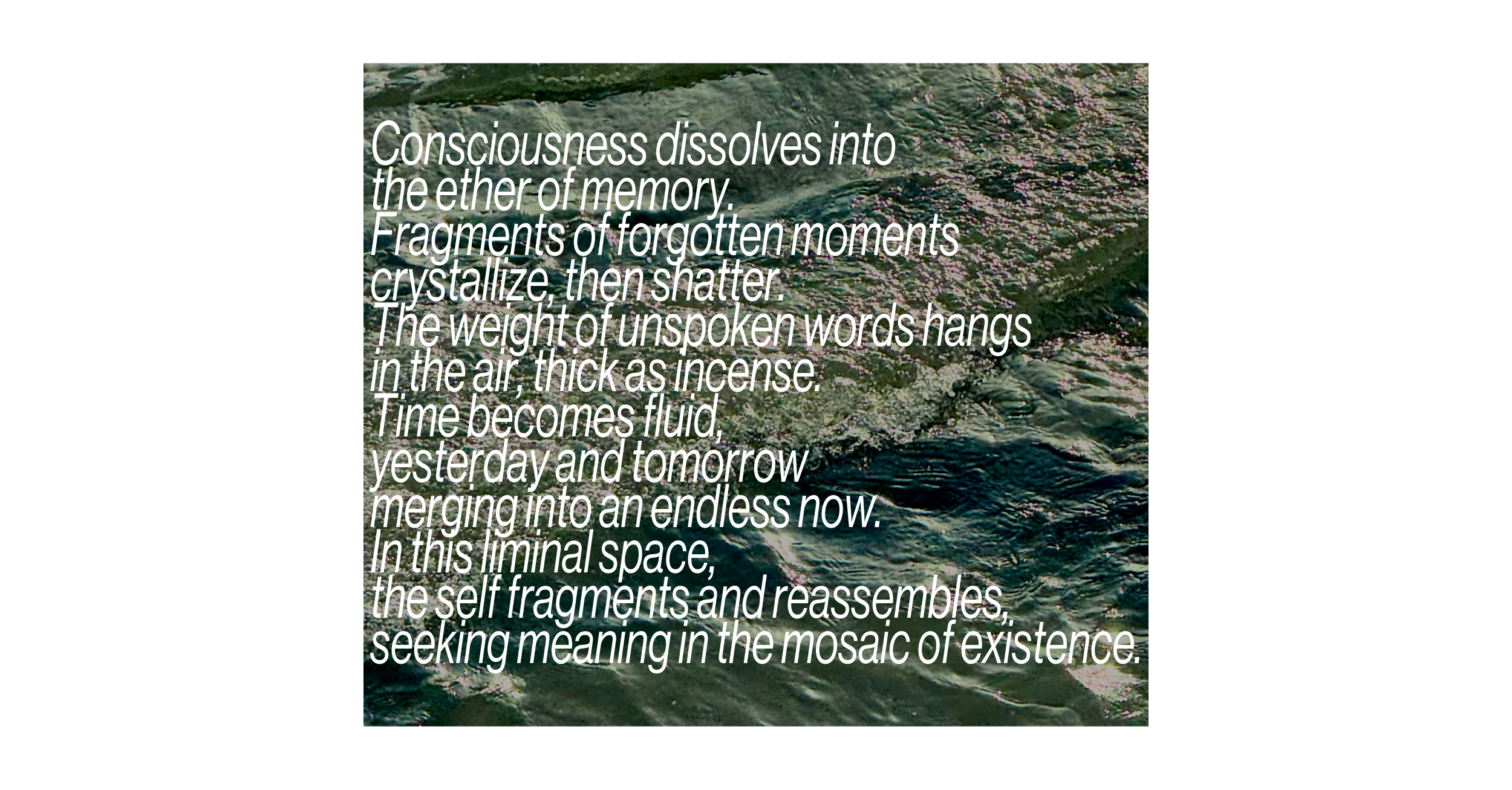時刻は午前3時。もうすぐおばけも寝静まる時間だ。時折過ぎる車の音だけが静かな室内に流れていた。その中に一等待っていた音が混じる。戸の音、足音、そして。
「おかえり。」
「……ただいま。」
待ってないで寝ろって言ったろ、そう言いつつ私を愛おしそうに見つめる君は、私が起きていることを期待していたでしょう?
「そもそも危ないから来るなって言ってるのに。本当お前俺がいないとダメだな。」
「ドンヒョクのほうでしょ、私がいないとダメなのは。」
「まあそれもそうだけど。」
私の腰掛けたベッドにそのまま倒れ込む傷だらけのきみ。
私たちは俗に言う幼なじみで、家も隣同士。物心着く前からずっと一緒だった。
中学生頃になって、私たちがおかしいことに気付いた。距離、温度に、お互いの感情が友愛だけじゃないってことにも。
思春期特有の距離が少し開いたあと、どちらともなく耐えられなくて、恋びとになった。
その時からもう既に彼はここら一帯の有名人で、高校生になってあまり宜しくない輩と絡むようになってからそれは決定的になった。
昔から運動神経が抜群に良くて、小さい時の諍いにも負けず嫌いもあって負けたことがなかった彼は、入学してしばらくした後、高校内の輩たちを仕切るようになったらしい。
“らしい”と伝聞形なのは、私は彼とは一緒の学校では無いからだ。私はそういった所には縁もゆかりも無い女子高に進学した。これもドンヒョクの勧めだった。だってそこは、あまり治安の良くないこの地域唯一のサンクチュアリだから。
「きょうも喧嘩?」
「そんなとこ。」
そんな風に会話しながら、残基ギリギリで帰還した彼の手当をするのが日課だった。
家が隣で、少し危ないけれど丁度ベランダからお互いの部屋に出入りできたのだ。
きっと染みるだろうに、その痛みにすら慣れてしまったのかいつも彼は私の膝の上で大人しく治療を受けている。
「わたし看護師にでもなろうか?そしたらいつでもドンヒョクの手当してあげられるし。」
「はは、いいかも。でも名前のナース姿、絶対えっちだから他の人に見せたくないなあ。もうシスターにでもなってよ。」
「何言ってるの、ばかじゃないの。」
軽く額を叩くと、ずっと固かった表情が少し柔らかくなる。今日はあんまりいい日じゃなかったんだろうなあ、なんて、私の思考が及ぶ範疇に彼はいない。
そもそも彼は、私にそういう所を見せないようにしているきらいもあるし。ちょっとくらい見せてくれてもいいのになあ、と思うけれど、私に許されたのは彼の傷をなでることだけだ。
「ドンヒョクは、将来どうするの?」
「うーん、考えたことないなあ。」
俺、生きてるかも分かんないよ。
そう言って頬に触れてくる手は少し震えていた。
「大丈夫。」
「何がだよ。」
」上に重ねた手のひらに、彼の不安も恐怖も伝わってくる。彼が何に怯えているのかは分からない。未来にかもしれないし、今このときかもしれない。
それでも、彼の涙を受け止められるのは自分だけだと言う優越感で心が昂る。何人も殴って、滅茶苦茶にして、絶望を味あわせて震わせてきたその拳が震えるのは、私の掌の中だけ。
「私がいる限り、ドンヒョクは死ねない。だって私を、守らなきゃでしょ?」
冷たい秋の風が私たちの間を通り抜ける。たった30センチの私たちの距離が、酷く遠く感じた。
「ねえ、ドンヒョク。」
「ごめんな。」
やさしいそのまなざしが、そのくちびると一緒に私を包んだ。
「明日を約束できない俺で、ごめん。」
感情を隠すように続けられたキスに、また遠さを感じる。それでいて、ふたりの密度が上がる度、彼の手にやどる温度にまた優越感に浸った。
どんなに遠い世界に生きているわたしたち2人でも、彼の汗と涙の両方の味を知っているのは、私だけなのだ。
ねえドンヒョク、私あなたが思っているほどきれいじゃないのよ。
「明日。帰ってきてね。絶対だよ。」
返事を求めない絶対も、きみを縛り付けたいから。だから。
そんなやさしい、キスをしないで。