体を起こしてベッドサイドに置いたペットボトルの水を飲む彼を眺めた。
いくら快楽に溺れたって、溺れさせたって、心はちっとも繋がらない。
恋なんてのは、落とし穴みたいに、嵌ってしまえば自分じゃあ戻って来られない。
それなのに、どうして。
青い月の明かりに、橙の間接照明が合わさって淡いグラデーションを彼に落としていた。絹のような綺麗な背中にひとつ、ふたつ、私の爪が描いた赤い線が残っていた。
運命の赤い糸なんかプラトニックなもの、この世にありはしないのだ。この世にあるのは、もっと残酷で、生々しい行為の残骸だけだ。
悲しくて、やりきれなくて、また泣いてしまいそうになった。慌てて目元を腕で覆う。
ああ、どうして、私はこの人の事を好きになってしまったんだろう。
「のむ、って、名前、泣いてる?」
見なかったことにして、おねがい。
知らんぷりをして。弱いわたしなんて、私の中だけに居ればいいの。
弱い私は許せないから。あなたもわたしも、なにもかも、許してあげられない。全部がだいきらいな、いやな私なんか、醜くて汚くて、捨ててしまいたいから。だから綺麗で清くて、大切なあなたの眼には入れたくないのに。
「名前。」
「いやだ。」
明確な冷たさを持って発されたその言葉は、綺麗に跳ね返って自分自身に突き刺さる。
さっきまで私の腰を掴んでいた彼の手が、さっきとは全く異なる温度で私の手首に触れた。
「どうしたの。なんか嫌な事しちゃった?」
「違う、ごめんなさい。」
「大丈夫だから。言ってみてよ。」
「本当に、私のせいだから、ごめん。」
急いで涙を店じまいさせて、愛想笑いを浮かべながら綺麗に畳まれたTシャツを手に取った。
彼に背中を向けてそれを被る。なんでこんなにダメなんだろう、私。ああ、全然うまくいかないなあ。
「名前。」
「ん?」
鼻腔にかかる声は、まだ完璧には戻れていない事を示していた。
「俺ってさ、そんなに頼りない?」
「え?」
「名前にとって俺は、泣き顔も見せられない?」
ひとさじの静寂と孤独とが混ざりあった白い部屋は、氷で出来ているようにも感じる。
「見せれないよ。だって。」
「だって?」
ベッドのスプリングが揺れる、私の横にドヨンが手をついたからだ。背中越しに覗き込まれる。そのとき考え事なんか一瞬すっと忘れてしまって、月みたいに綺麗な人だ、と思った。美しい弧を描く瞼も、新月のような藍さの虹彩も、全部。
「だって。」
「うん?」
「……だって。」
すん、と鼻をすする。少し待ってくれたあと、いじわるだったね、と申し無さげな笑みを浮かべ私に水を手渡して彼はベッドを離れようとする。
いつもこうだった。誰かが手を差し伸べてくれても、それを掴むことが出来なかった。
自分の気持ちを口にしようとすると、饒舌なはずの口が、喉が、全くと言うほど開かなくなってしまう。頭が真っ白になって、心も空っぽになった。
私って本当は何も考えていなくて、全部虚構で作り上げていただけなのかもしれない、とすら思ってしまう。
以前1度だけ、自分から彼に縋ったことがあった。少し酔っていたし夜中だったから出来たんだと思う。深夜2時に発信ボタンを押して、それから後悔した。もし向こう側に私以外がいたら、と。急いで切ろうとしたけれど、優しい何時もの、それでいて少し掠れた寝起きの声がして安心した。けれど起こしてしまったと思ったら申し訳なくなって、なんとか適当なことを言って電話を切った。
そう言えばそれからだったかもしれない。彼がキスをやめたのは。
彼のキスの、甘やかすような、ゆったりとした温かい感触が恋しくなった。
気が付いたら自分のくちびるに手が伸びていた。自分の指をあてがった所で、同じ感触なんか味わえっこないのは分かっているはずだった。
「これ、体拭きな。俺シャワー浴びてくるから。」
「ありがと。」
彼なりの気遣いだろう、1人にしてやろう、という。そして私は、また誰かの手を掴み損ねている。もし可愛げのある女だったら、風呂場に向かう彼を後ろから抱きついて止めるだろうか。
ベッドに寝っ転がって逆さまの世界越しに彼の背中を見たけれど、自分がそんなことをしているのを想像したら反吐が出そうだった。似合わなすぎる。
渡された蒸したタオルはあっという間に温度を失う。情事のあとの私たちみたいに。
このタオルと一緒で、私たちは世界に温かさを持ち続ける事を許されていない。世界が許さない根拠が物理法則か倫理かの違いだけで、私はこいつとほとんど変わらないのだな、と思うと広げたタオルに愛着すら湧きそうになった。
「あーあ。好き、なんて言えればなあ。」
虚空に溶けたかと思っていたその言葉は、思わぬ顛末を私に与える。
「……好きなやつ、いるの?」
「へ?なんで居るの!」
今世紀最大に滑稽な姿を見せたような気がする。
飛び起きて声のした方を向くと肩にタオルを掛けて濡れた髪から水を滴らせる彼の姿──水も滴る良い男──が見える。
「はや、く、ない?」
「え、いや?その……名前が早く入りたいだろうな、と思って。」
「あー…ありがと。」
なんだか嘘くさい言い訳にも聞こえるが、半分くらいはきっと本心だろう。
じゃあ入ってくるね、と立ち上がってフローリングをペち、と鳴らした。
優しい君のことだ、結局なんだかんだ私のことが心配になってしまったのかもしれない。
「待って。」
手首を引かれ、半分ほど抱擁されるような形になってしまう。シャワー上がりのほかほかな彼に可愛げを感じてしまうあたり末期だろう。
「な、なに?」
「だから、好きな人。いるの?」
ほとんど20センチ上からこの距離で話しかけられると首が痛い。また何も言えなくなって、ああ、とかううん、とか、言葉にならない音を発してなんとか誤魔化そうとしたけれど、珍しく諦めの悪い彼は食い下がってくる。
「……いるなら俺たち、ちゃんと辞めよう。」
ぎゅっと掴まれた手首が痛む。心も。
自分すら愛せない人に他人を愛することなんか出来ないと言われるけれど、これは愛じゃないのだろうか。
私の手首が赤くなっている事にも気づかないほどの君が、私を離したくないと思っていると、思い込んでしまいたかった。
「なんで、なんで名前がそんな顔するんだよ。」
私はいま、どんな顔をしているだろうか。
確かに視界は歪んでまともに何も見えていない。決壊ぎりぎりまで溜まった涙を流さまいと必死にこらえている。きっと間抜け面だろうな。
私は何度この男に泣かされるのだろう。自分が泣かせた、なんて露程も思っていなさそうなこの男に。きっと誰にでも優しいきみに。
「……俺じゃあ、駄目だった?」
だめじゃない、駄目なんか、そんな訳あるか。ずっと君が良いのに。君の隣に並べるほど出来た人間じゃないから苦しいんじゃないか。そんな事も知らないくせに、自分じゃ駄目か、なんか聞かないで。勘違いしてしまう。君が『自分であればよかった』と望んでいるように聞こえてしまう。私のただ一人が、自分なら良かった、とそういっているんじゃないかって、都合の良い解釈をしそうになってしまうから。
だからそんなふうなそんなセリフを言わないで。
もう涙はとっくに堪えきれなくなって好き勝手に顔を伝っている。つぎの一言を、どうにかして紡ごうとして、顔を上げた。
視線がかち合う。
ミッドナイト・ブルーが私たちを包み込んでいた。
「だめ、」
つよくて、やわらかい。
その人そのものに触れたような、そんな気がした。
「まって、」
続けて食まれ続ける狭間、やっと口にした制止の言葉。
知ったことか、とあっという間に舌ごと飲まれる。
あつくて、でも慈しみに溢れている。
ずっと私が求めていたものだった。
交わされる熱と粘膜の触れ合いが懐かしく、魂の底からもっと、もっと、という渇望が生まれる。
私たちの間に少しある身長差なんて気にも止めず、縋るように首に手を回した。
すぐに感情なんか生物としての欲求に飲まれてしまうんだと教えこまれるみたいに。
涙がずっと流れている。悲しいのに、気持ちよくて、いとおしい。
やっと落ち着く頃には、ふたりともまた汗だくになっていた。
「……ごめん。」
いつの間にか追い込まれた壁際で、汚れた口元を拭いながら放たれた謝罪の言葉は一体どこに収めるべきなのだろうか。
何か返さなきゃと、はくはくと言葉を探して口を動かしてもなにひとつ適切なものが見つからなくて戸惑ってしまう。
「あの。」
「うん。」
「駄目じゃない、くて。」
「……うん。」
「だから。」
「ゆっくりでいいよ。」
そう笑って、ぽろぽろと落ちる涙を掬ってくれる骨ばった指が愛おしかった。
もう涙に感情は込められておらず、半ば生理現象かのように流れ落ちている。
「……ごめんね。」
震えた声で、彼に投げかけたその言葉の真意がどこにあるのか、一体私は何に謝っているのか、もうよくわからなかった。
とにかく、この胸の支えから、苦しさから解放されたかった。誰でもいいから、わたしを許してくれたら、きっと楽になれるんだと思った。
「大丈夫、名前のこと分かってるから。」
時折ドライヤーをサボったせいでパサつく髪を彼が撫で付ける。こんな情緒のときでさえ、そんなことが気になる私はいやな人だ。
「ちょっとずつ、教えて。」
それから、と彼は私の耳を触りながら続けた。
「ごめんじゃなくて、ありがとうが良い。」
「……ありがと。」
壁際で、汗をかきながら立っているのがやっとなほどに泣きわめくわたしは、その瞬間は、たぶんこの世でいちばん滑稽で、かなしくて、それでいて幸せものだった。
FRI PM 23:01
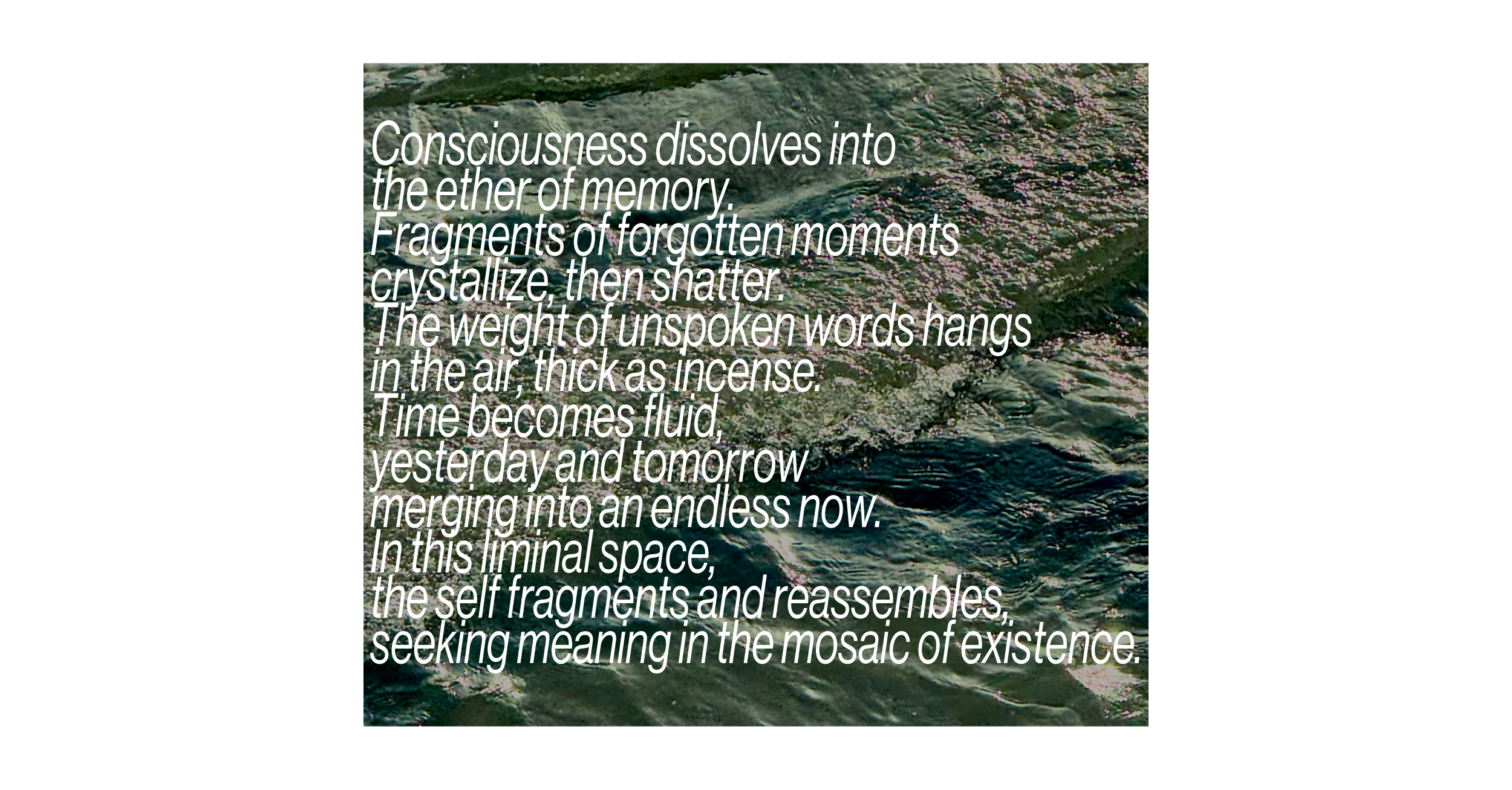 WITHOUT U
WITHOUT U