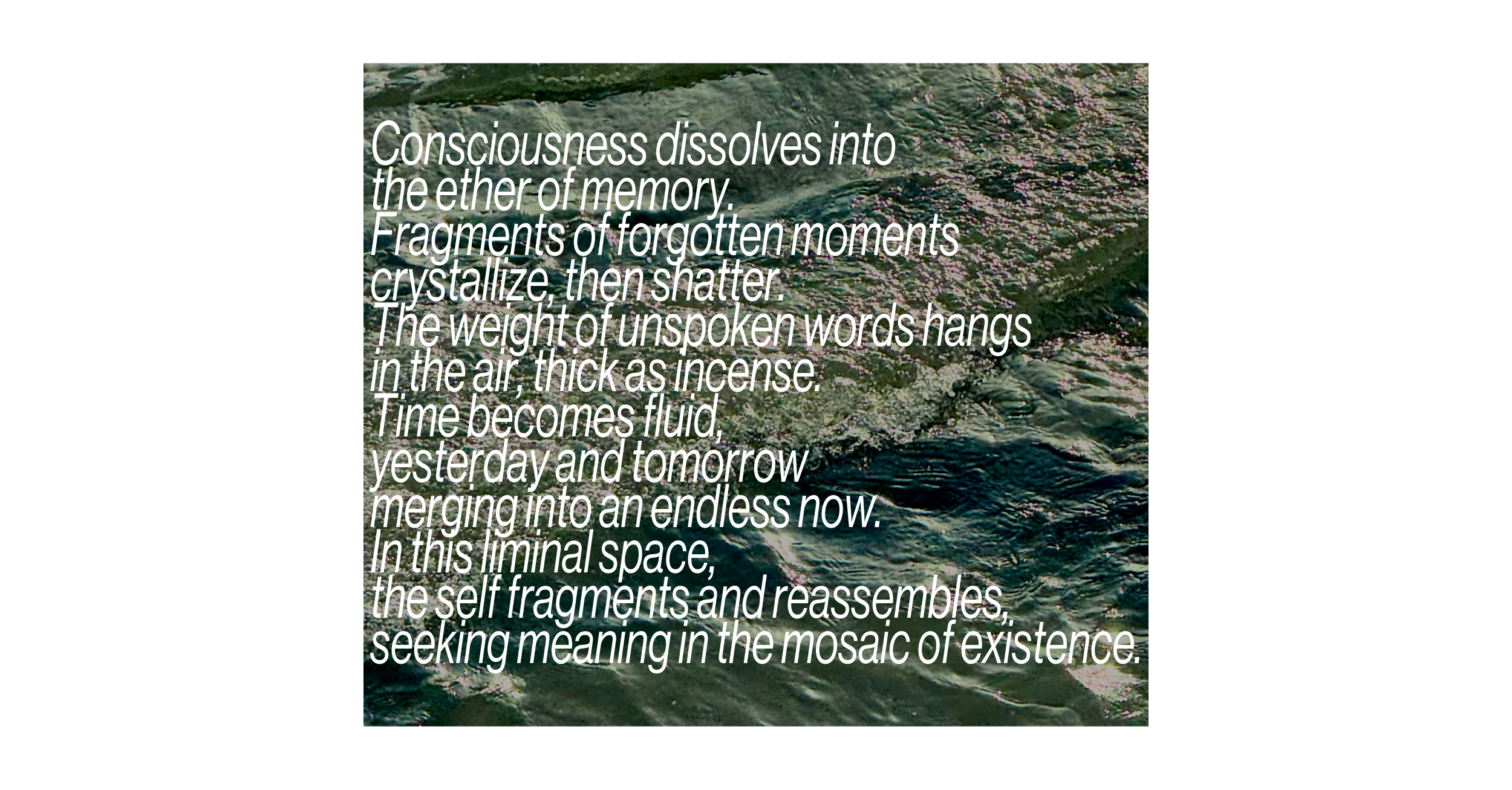「名前ちゃん何飲む?」
「あ、えーと…カシオレで。」
「かわいいね〜。あ、俺は生で。」
隣から話しかけてきて、何となく触ろうとしてくる男。最近寒くなったね、じゃねえんだよ。私はあんたに温もりなんて求めてない。
そう、ここはサークルの飲み会。なんの為かも分からない、特に理由はなさそうなのに名前の付いている行事。飲みたいだけなら最もらしい理由なんて付けずに、ただそれでいればいいのに。
「カンパーイ!」
ぶつかり合う黄金。ガヤガヤと両隣とジョッキやグラスを突き合わせて意味のない作り笑いを浮かべた。私が笑いかけたかったのはこの人じゃないのに。
「あれ? ジェミンくん珍しいね。」
そんな中一人、遅れてすみませんなんて笑いながら入ってきた彼。そう、彼こそが私が笑いかけたかった人─ナ・ジェミンだ。
ヤリサーと部活のちょうど中間を行くザ・普通のこのテニスサークルに、唯一咲いた花みたいな存在だった。今年入った新入生の3分の1は彼目当てで、もう3分の1は彼目当ての女の子のおこぼれを狙ったバカな男だち。かっこよくて、優しくて、テニスも上手だった。高校生のときに県大会で優勝したと聞いた気がする。
そんな彼が飲み会に出てくるのは年末年始・歓送迎会くらいのものだったけれど、今日は珍しくなんにもない日なのに彼が飲み会に来ていた。
彼と仲良くなったきっかけは春先の連休にあったプチ合宿という名の新歓旅行で、語学が一緒のクラスだった彼が私に話しかけてくれて同じ班になった事がきっかけだった。
私はひどい人見知りで、中高となんとなく続けたテニスをまた大学でもなんとなく続けてみただけ。先輩が親切そうだったこのサークルを一人で選んでしまったから友達どころか知り合いもいなかった。多分合宿前から彼お目当てで入った人たちの中で彼に興味も無さそうにしていた私はすっかり浮いていたんだと思う。彼は『なんか幼馴染に似てるから構いたくなっちゃった』と言っていたけど、気を使わせないように嘘を吐いてくれたんだろうな。本当の陽キャは陰キャにも優しいって本当だったんだ。
その後の合宿はというと、結局のところ彼とあとは新歓で声を掛けてくれた優しそうな女の先輩とだけ話した。ジェミンが自発的に話しかけている女の子は私くらいだったから囲いの女の子たちからの視線が痛くて、とても親睦を深めるといった空気ではなかったのだ。この点このサークルはちょっとそちら寄りになってしまったと言えるかもしれない。
合宿の後もサークルと週2の授業を合わせたらほとんど毎日彼と顔を合わせる毎日が続いた。被っている授業がいくつかある事も分かって、そのうちのいくつかは一緒に隣の席で受けるようになったし、流れで学食に一緒に行くことも増えた。気がついたら、私は一日の半分くらいを彼と共に過ごしていた。彼の好きな食べ物も、彼のバイト先も、趣味も知っているのは私だけ。そう思うと今までよりも毎日が輝いて見える。きらきらを詰めた宝箱を持ち歩いている気分だった。
「この後あの眠くなる教授かー、やっぱりご飯食べた後のあの教授キツイよ。」
「名前ちゃん昨日夜シフトだったんだっけ?」
「そう、だから余計に眠いの。」
「しょうがないなあ、出席だけしたら寝な。ナナ起こしてあげるから。」
「え、本当?やった。」
後でちゃんとノート写しなよ、とまで付け加えてくれる彼は、追加のアメリカーノをテイクアウトしていた。ジェミンもそんなに授業起きているタイプじゃないのは仲良くなる前に見ていたから知っている。コーヒーを飲んでまで私のために起きててくれるのか、と自惚れてもいいのかな。
教室に入って、後ろの方の一番奥の席に二人で座る。端の方がバレにくいから、そう知ってるってことは君もやっぱり寝るタイプだったんじゃないか。
「これ掛けときな。」
そう言ってジャケットを私に貸してくれるジェミンの王子様ムーヴは留まることを知らない。ふつうの女の子なら会った瞬間に君のこと好きになっちゃうのに、これに耐えている私は一体どうなっちゃうんだろう。心臓がうるさくて、でもそれが彼にバレるのはなんか嫌で眠いふりをして生返事で必死に反対側を向いて目を瞑る。お願いだから治まって、そう思うのに、肩に掛けられた彼のジャケットから香るブラックベリーがどうしても胸を騒がしくする。
どうかあなたにはこの音が聞こえませんように。目を強く瞑って祈っている間に本当に眠ってしまったみたいで、次に気がついたのはジェミンが投げ出された私の手を擦りながら私の名前を呼んだ時だった。
「えあっ!?」
「ふふ。そんなにびっくりしなくていいんじゃない?」
目が覚めた時普通イケメンが目の前で自分の手を握ってたら普通は驚くんだよ、ジェミナ。そう言わないであげた私の優しさに敬意を払ってほしいくらいだ。嘘、本当は心臓がバクバクでそれどころじゃなかった。
「待って、終わって何分経ってるの……?」
「ん?30分くらいだけど。」
「終わったら起こすって言ったよね?」
「起こすとは言ったけど終わったらとは言ってないよ〜!」
楽しそうに笑う目の間の美丈夫をもう私は信じられそうにない。それって授業が終わってから私のことずっと見てたって事?なにそれ、そんなのジェミンが私のこと好きみたいじゃん。それに気付いた途端、相変わらず私の手で遊ぶジェミンに私は何も言えなくなってしまった。目が合わせられない。初夏の生ぬるい風だけが流れる。
「名前ちゃん?」
「……なに。」
「ううん、帰ろうか。」
そうやって簡単に離された手を寂しいと思ってしまった。私はもうきっと彼におかしくされてしまった。そして、きっと君にこの鼓動は聞こえてしまったんだ。夕刻の赤い時間が秘密を覆い隠してくれるわけじゃない。
今思うと、彼は最初から私の事をこの時みたいに手のひらで転がしていただけかもしれない。
いつの間にかサークルの外の友人には付き合ってるの?と聞かれるくらいずっと一緒にいるようになった私とジェミン。それからも私に構い倒し、挙げ句秋学期の履修は一緒にしようね、なんて言って本当に全部一緒にしてしまった。春学期のはじめに彼と仲の良かったはずのドンヒョクくんはもう学年一のプレイボーイだというのに、ジェミンは私と一緒に居て何が楽しいんだろう。そう気になって本人に聞いたら、『名前を見てるだけで楽しい』と言われてしまって食堂で顔をトマトにしてしまった。恥ずかしいことこの上なかった。
それから、休日に二人で水族館に行ったりプラネタリウムに行った。ジェミンが選ぶ行き先は大抵静かで、穏やかなところだった。でも普段学校では分からなかったジェミンの性格(ちょっと変)だったり、私たち二人は意外と話さなくてもお互いリラックス出来ること、たくさん発見があって面白くて、秘密主義な彼の世界を見ることを許されたみたいで嬉しかった。
ああ、私この人のこと好き。それで、多分この人も私のこと好きだ。きっとこの人とお付き合いして、そのうち手を繋ぐ以上のこともして、幸せに二人でアイスクリームを分け合ったりするんだ。そう思っていたのに。
「あれ?名前ちゃんジェミンくんと仲いいのに知らなかったんだ?」
ある日、サークルの数少ない友人から聞いたのは衝撃的な事実。
それは、春合宿で私が唯一お話していた先輩とジェミンくんが付き合っているという噂だった。