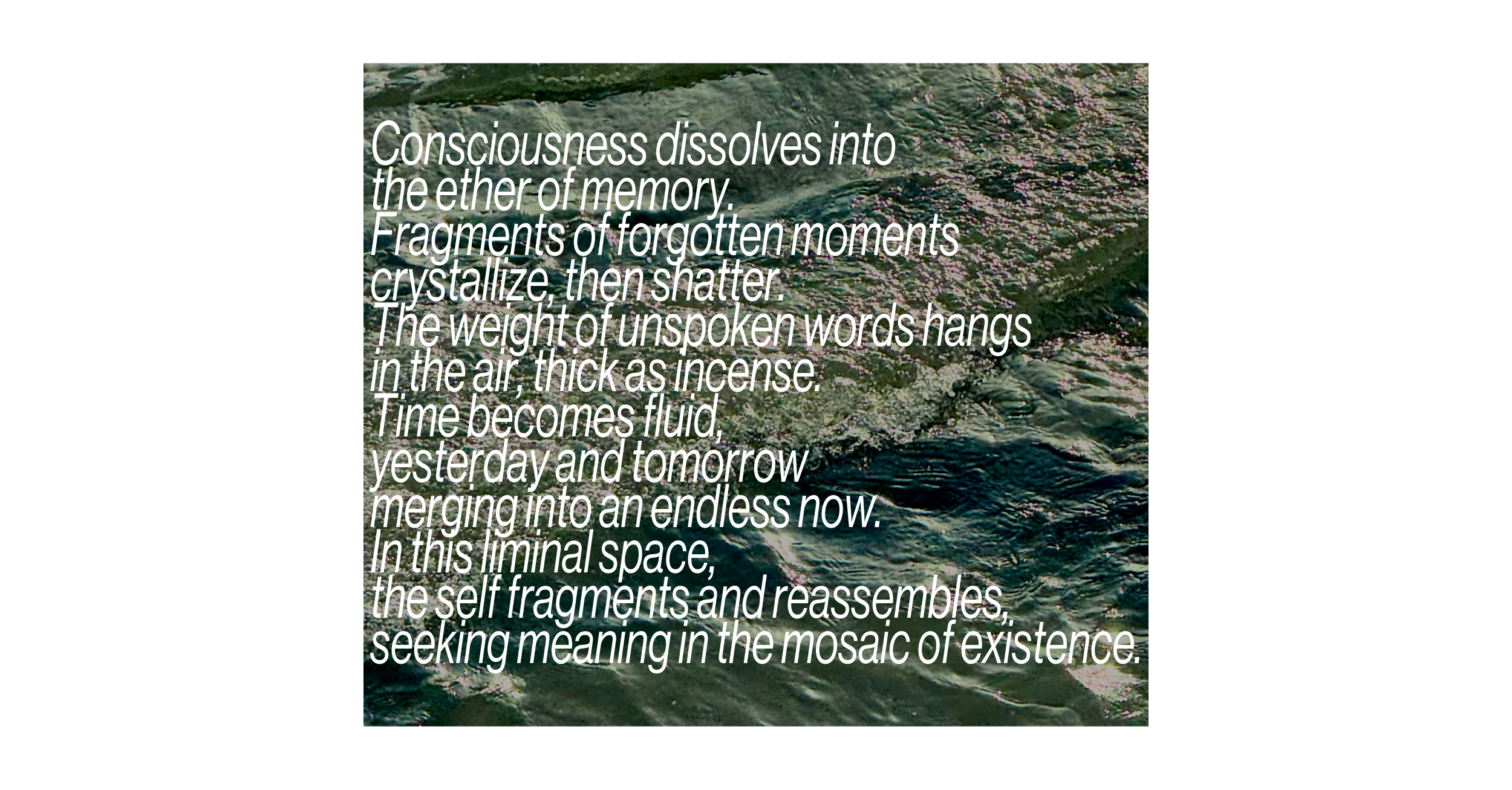きみとのぞむあさひがこんなに美しかっただなんて、ちっとも知らなかったや。
「うわ、またいるんだけど。」
「何だよ、この前業スーにしか売ってないお酒飲みたいって言ったからわざわざ学校帰りに買ってきてあげたのに!」
キム・ジョンウ。文学部仏文科2年。
よくわからない”おさんぽサークル”なんて甘い皮を被った悪の組織でニコニコと愛想の良い笑みを浮かべて近付いてきて、それからずっとダラダラと友人関係を続けている男。
驚くほど、私たち二人の間には何もない。ただこうして時折フラっと家へやってきてお酒を飲んで帰っていく、そんな人だった。
肉体関係を迫られた事も無ければ、大学生特有の悪ノリすら振られた事もない。
飲み会なんかでは明るくお酒に飲んで呑まれてをしているので別にそういうのに興味がない訳じゃなさそうだったけれど、まあ、都合の良い女は他にもたくさんいるんだろう。
なんてったって大学随一のイケメンだ。私くらいのレベルの女なんて、酒のアテぐらいにしかならないとでも思っているのか。
「……ジョンウって女の子の家の合鍵何個持ってる訳?」
「人聞き悪いよ〜1個も持ってないって。」
「そんなこと言ったって、ねえ……。」
「限定モモ味、いらないの?」
「いるけどさあ。」
いつの間にか置きっぱなしにされるようになった彼のボクサーパンツとくたびれたTシャツに、洗面所に増えた歯ブラシと歯磨き粉に、不満を抱くことはなかった。
でも、彼にとって私が何なのか。私はここのところすっかり考え込んでしまっていた。
彼は大学じゃ有名な美青年で、ミスターコンに出るように毎年言われているのにも関わらず決して出ようとしない。
彼女が嫉妬深いのかと思いきや、女の子の影があるわけでもなくて。
こんなに私の家に入り浸っていいのかと不安になって恋人の存在を探ったときもちっとも嗅ぎ取る事が出来なかった。
だから、特定の人を作らないでこうやっていろんな人のところを渡り歩いているんだ、と、そう勝手に考えている。
別にそれで良かった。
きっと少しだけ、浮かれていた。その都合の良い女に選ばれた事に。
なんだか邦ロックの下品な歌みたいで、やっと自分が理想にしていた大学生になれたみたいな気がして。
だからずっと、関係を問い直す事もせず、ただ甘んじていた。
それに、拒まれるのも怖かった。今の関係が壊れるくらいなら、余裕な女を演じて捨てられてやってもいいんじゃないか、とかバカな事を妄想していた。
のんきに私のくまちゃんを抱きかかえながら出前で頼むチキンの味を私に聞く彼をジト目で睨んだところで、彼が気付くはずもない。
こうして彼と自分の関係に疑問を抱き始めてしまったのは、上京してきた1つ下の幼馴染のせいなのだ。
彼と少し雰囲気が似た、身長が高くて顔のきれいな男だった。
成人祝いに家にあげてお酒を二人で飲んだとき、「ヌナ彼氏いるんですか?」と聞かれた。そりゃあこんな部屋の様子で男の気配を感じるな、という方が無理な話だろう。
でも、なにも答えられなかった。
だってセフレですらないのだ。ただ家に来て酒を飲んで帰っていくおとこ。私を1限のアラームとしか思っていなそうな男。
「ヌナ、彼氏いないなら僕と付き合ってくださいよ。」
そういった言葉が飛び出たのはお酒の力ゆえなのか、それとも彼がずっと思いを胸に秘めていたのか。私に知るよしはない。
けれど多分、それに誠実に答える責任はある、と思った。
飲ませたのも、そういう隙を見せたのも私だから。
正直、まったく嫌じゃなかった。
だからこそ悩んでいる。実家ウケも良い、将来もちゃんと考えられる気立ての良い青年なのだ、幼馴染は。
それに引き換え目の前の男は──ブリーチしたはずなのにサラサラな白髪を称えた、色の白い綺麗な人──紹介できるか、ちょっと疑問だ。
ジョンウは自分は大して酒好きじゃないくせに、私のためにせっせと酒を買ってくる。もうちっともわからない。
23時を告げる就寝アラームが、意味の無い通知音を鳴らした。
「缶詰のモモ入れて飲んだらおいしいと思って買っておいたけど?」
それに甘えて、来る事を期待して準備している私だって大概なおんななのに。
「さすが名前は違うわ〜久しぶりにいっぱい飲んじゃおうかな。」
「明日吐かれるのいやだからやめて。」
「介抱してくれないの?」
「やだよ、てか明日予定あるし。」
「なんの?」
「ジョンウには関係ない用事だよ。ほら、桃入れてあげたから楽しくなりな。」
真っ赤な嘘だ。関係ないだなんて。
明日は。
「ソンチャンとデート、でしょ?」
「な、知ってたの?」
「あの子、わざわざ僕のとこ来て『あなたと懇意にしている女性は僕の幼馴染で、結婚を前提としたお付き合いを申し込みました』って報告しに来たから知ってる。」
「あっそ、じゃあそういうことだから。」
「僕が服選んだあげようか?」
遠慮しておく、なんて軽口を交わしながらグラスに口をつけた。切子細工が気に入っているものだ。これもそう言えば、いつの間にかジョンウが家に置いていったものだ。
なんとなく、残念だと思った。これを処分しなきゃいけないのは惜しい。
でも、デートを知って止めないって、そういうことだ。
桃味の酒に溶けた缶詰のあまいシロップが舌にもつれる。そのうち消えてしまうその甘さの名残を追うように、またひとくち口に含む。
「あの子、名前のこと好きなんでしょ?」
「そうだと思ってるけど。」
ふーんとか、そっか、とか。どうでも良さそうな返事をしている彼のグラスはいつの間にか桃の果肉だけが残されていた。
ジョンウは空になったそれに、ジャンクショップの黄色い袋からおもむろに違うお酒を出してトクトクと注いでいる。
「今日は良く飲むね、なんかあったの?」
「名前には関係ない事だから。」
そして私もふーんとか、そっか、とか、とても興味のなさそうな声で一度に残りを煽った。
珍しくほんのりと頬が熱くなる感覚がして、ああ、酔っ払ったんだ、とぼんやりとした思考が感覚を追う。
2人して適当な返事ばかりで、楽しそうな様子もない。
ずっとこんな感じだ、この人は。
いつも私が飲む様子を見て楽しんでいるらしい。別に酔っ払う訳でも無いのに何が楽しいんだろう。
「名前は何飲んでるの?」
「適当に混ぜたなんか?よくわかんない。」
家にあったテキーラとオレンジジュースと、あとその辺にあったリキュールを混ぜた。
「そんな強くないからジョンウでも飲めると思うよ、飲む?」
「え、あ、うん。貰おっかな?」
そのままグラスを手渡す。
口を付けたところを上手く避けて飲むジョンウは器用だな、なんてよく分からない事を考えて口元を見つめていた。
私って案外この男のことを気に入っていたのかもしれない。今更気付いたけれど、もう遅い。
きっと家から少しずつ物が無くなって言って、彼の匂いが消えていくんだろう。
「明日早いから、そろそろ帰って。」
そんな言葉を彼に告げたのは、深夜2時ごろだっただろうか。
徒歩圏内に1人で住んでいるのは知っている。だからこそこの男は毎度懲りずに私の家でダラダラと飲んでいる。
少し離れたところにいるジョンウは、俯いたままちっとも返事のひとつもない。
私はぺちり、と裸足の足音を立てながらショートパンツの裾を揺らして彼に近づいた。
「ねえ、寝てんの?」
変わらず、部屋には均等な間隔で音を刻む時計と、時折する風の音だけがしていた。
そう言えば明日は大雨の予報が出ていたんだっけ。なら尚更、早く帰さないと。
「ちょっと、起きて。」
「やだ。」
「やじゃない。」
ほら、と彼の肩を揺する。
片手に空の水のペットボトルを握りしめる彼は相当酔っ払ったみたいで、耳まで赤くなっていた。
「……かえりたくない。」
「いや帰ってよ、言ったじゃん。」
彼の肩口に立っている私の腰あたりが来て、いやはやしかし大きな赤子だ、とため息をついた。
小さい子みたいに私のTシャツの裾を掴んで離さないジョンウに呆れつつも結局許してしまうのは、私の弱さだ。
それも今日で終わりにしなくちゃ、そう思って彼の指に手をかけた。
か細くて脆そうなイメージだったそれは思っていたより男性らしく大きかった。こんなことも、知らぬまま。
秒針の音が一際大きく聞こえた。カーテンの隙間から覗く月のひかりが、その時だけはわたしたちふたりだけを照らしていた。
彼の手に触れた途端に指は絡め取られ、そのまま向けていた背は彼に覆われる。大きな彼の影がわたしを月から隠してしまって、ほんの少しのアルコールとタール、それに彼の香水のローズが鼻腔を擽った。
「帰りたくないんだってば。」
今まで聞いたことの無い語気の強さだった。
「聞けないよ。」
だってもう私、違う人の彼女になるんだから。
こんなに距離を詰められたのも初めてだった。いつも冷たく思っていたのに、この人はこんなにひとの温度がするのか。
時計より早いスピードで進む彼の鼓動を聞きながら、肌に伝わる湿度をじんわり感じた。
「俺がいるじゃん。」
「え?」
「そもそも、俺がいるのになんで他の男家に入れてるんだよ。」
「だって別に、ジョンウは、」
くるりと振り向かされ、くちびるが塞がる。
柔らかな感触と熱い手のひらに、頬が赤くなる感覚がする。
長いまつ毛がほんの少し私の薄い肌を掠めて、それから少しして離れていった。
子鹿のような瞳と目線が交差して、止まってしまった。
「これでも?俺たちはただの友達なわけ?」
至近距離で動かされる彼の唇にどうしても目線が行ってしまう。思考がままならない。
「……だって。」
「こんなに俺にキスされてドキドキしてるのに?」
そんなこと、私が1番わかってるのに!そもそも、微妙な関係のままうちに入り浸り始めたジョンウのせいなのに!
苛立ちのまま、目の前のジョンウの胸を思い切り殴った。もう知らない。殴り続けた。
黙って受けているのにも飽きたのか、突然腕を取られる。抵抗虚しくいとも簡単に自由を奪われ、そのまま腕は殴っていたはずの胸にそっと当てられた。
「ジョンウも人のこと、言えないじゃん。」
「当たり前じゃん。好きな女の子の家にいて、キスまでしたんだから。」
それって、と口にして顔を上げた。ジョンウの表情は初めて見るくらい真剣で、私が期待したいつものへらり、とした笑みはどこかへ消え去ってしまっていた。
「俺、名前のこと好きだよ。」
今までそんなふうな雰囲気も出したこと無かったのに、とか、もっと早く言ってよ、とか。
色々言いたいことが頭の中に浮かぶのに、上手く言葉に出来なくて霧散して行く。
ぜんぶぜんぶ、ジョンウに見つめられて離してもらえないせいだ。
「俺たち、そろそろ付き合うべきじゃない?」
そう言われて絞り出せたのは、たったの一言だけだった。
「……勝手な人。」
毒づいたはずなのに、勝手に上がる口角が隠しきれない。
もう一度、彼の胸をぺし、と叩くと、そのまま肩と背中に腕を回され抱きすくめられてしまった。
「あーあ、もっと早く言った方が良かった?」
「当たり前じゃん、ずっと、」
「ずっと?」
「……ずっと、待ってた。」
なんだよそれ、と笑う君の耳が赤いのを知っている。
ああ好きだ、と。愛してる、と。ぽつり、空に溶けた息に混じっていく。
これが満月の見せた夢でないことを祈った。
「わたしも、あいしてる。」
愛なんて分からないけれど、愛してる、って言葉で、無理な背伸びが10センチヒールくらいの苦しさに収まる気がした。
「もう1回、キスして。」
「1回で足りるの?」
夜明けまであと2時間。
寂しさから逃げ出したくて、田舎のこどもから抜け出したくて走り出した。いつの間にか何だか遠くまで来てしまったんだなあ、と、惚けたように考える。
淡く重なるキスが段々と濃厚なものになっていき、舌でこじ開けられた唇の隙間から真っ赤な果実が踏み込んできた。
ふとうっすら目を開くと、いつもの子犬はそこにいない。
ただ男の顔をした美しいひとが、必死になって私の舌を絡めとっていた。
今まで繋がらなかった時間を埋めるかのようにじっとりと交わされる口付けがなんだか少しもどかしい。
私は彼のTシャツの裾に手をかけて、その下の絹のような素肌に触れた。
「名前。」
私の名前を呼んで途中まで捲りあげたTシャツを投げ捨て、月の光の元に磨かれたからだを晒すジョンウは神話の登場人物みたいだ。
「ぜんぶ、名前の全部、俺にちょうだい。」