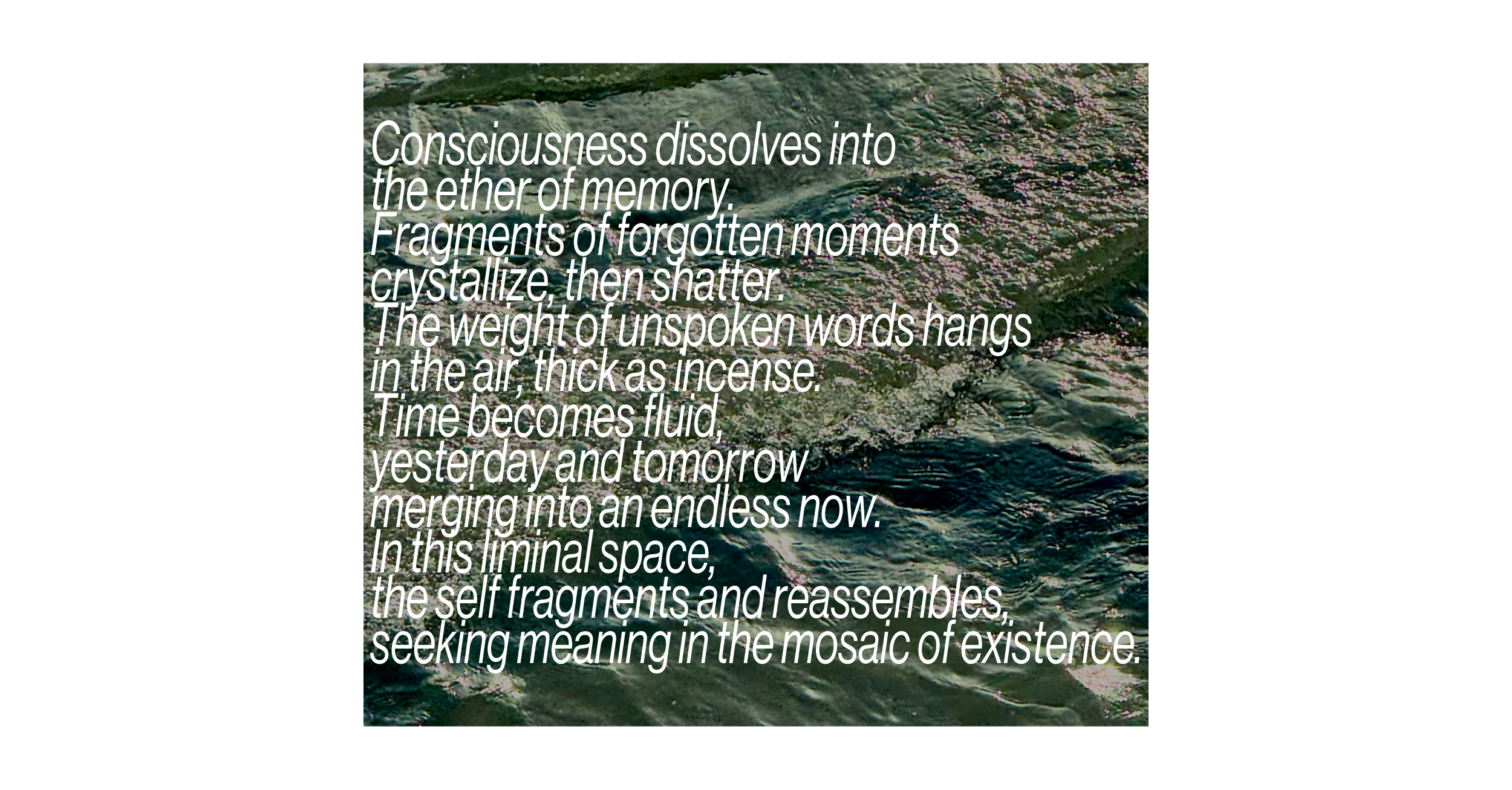3月が始まった。
街には卒業証書を持った子たちが歩くことも増え、胸元の『卒業おめでとう』の花が輝かしい。すっかり風も温かさを含んで、さくらの蕾はもうすぐ来る開花を待ち望んでいる。
そんな中で私は春眠暁を覚えず……と言おうか、ベットとねんごろになっていた。新調したリネン、これが最高で、布団を引き上げた時に顔に当たるふんわりとした感触がたまらない。
「ん、おはよ。」
まっしろな繭から手を伸ばし、掠れた声でほとんど形にならない朝の挨拶を交わす彼の頬を撫でた。じゃり、とした髭の感覚がなんだか可愛く思えていつもそうしてしまう。
「まだ寝る?」
「ん、もうちょっと。」
今日は2人でコーヒーを挽いて、フレンチトーストを焼こう、昨日の夜まではきちんとそんなおしゃれな朝を夢見ていた。
つまるところ、二度寝の誘惑に負けた。
それは彼も同じらしく、彼は同意の言葉と共にやさしく私を引き寄せる。
昨夜の情事の痕すらも朝の柔らかな光にかかれば生々しさはどこか遠くに飛ばされて、映画のワンシーンみたいに見えた。
私が彼の胸の花弁を撫でる時、彼は私の髪を梳く。
「髪、そろそろ染め直す?」
「うん。」
だいぶ伸びたね、と暢気に言うけど、美容師さんにまで嫉妬する君のせいで、一時期苦労したんだから。
同窓会もゼミの打ち上げもなんともない顔で私を送り出したくせに、私の行きつけの美容院で男の人に髪を切ってもらってるって言ったら凄い剣幕だった。
忘れたくても忘れられない思い出だ。迎えに来た彼とお見送りの美容師さんが鉢合わせた時の彼の顔と言ったら!
彼は所謂髪フェチ、というか、彼にとって髪は胸とお尻の次に重要なセックス・ポイントらしい。時々アレンジやお手入れをしたがるのでやらせている。
彼は一人っ子だったみたいだから、漠然と私を母親の姿と重ねているのかもしれない。お金持ちの家みたいだったし、家族で出かける前、ドレッサーの前で化粧をして髪を巻く母親の姿を彼は見ていたんだろう。“女”になる自分の母親を。
いつまでたっても男の人って、母を忘れられないものだ。
「今日は三つ編みにしようか?」
「なんでもいいよ。」
私より私の事をよく見ているので、自分で決めるより彼が決めた方が何事も私に良く似合っていた。どうせ今日の服も彼が決めるのだろう。
はだかの私を知っているのは、彼だけだ。
きっと君は、その優越感に酔っている。
「ね、私今日お花屋さんに行きたい。」
「チューリップとか?」
「うーん、ミモザもいいかも。」
でも大きな花瓶がなかったかな、と引き出しの中身を思い浮かべた。
「何の花でも似合うよ。」
「私じゃなくて、部屋に合うかじゃない?」
何が楽しいのか、かわいい笑窪を作って首をなぞる彼に疑問符を投げかける。私のことが大好きなのは分かったけれど、最近は褒め方が雑だ。
「細かいことは気にしない〜。」
「ねえ、ちょっと!そういうことするなら起きる!」
ああ、なんだかオレンジジュースが飲みたい。
スペイン語で「オレンジの片割れ」─運命の人のこと