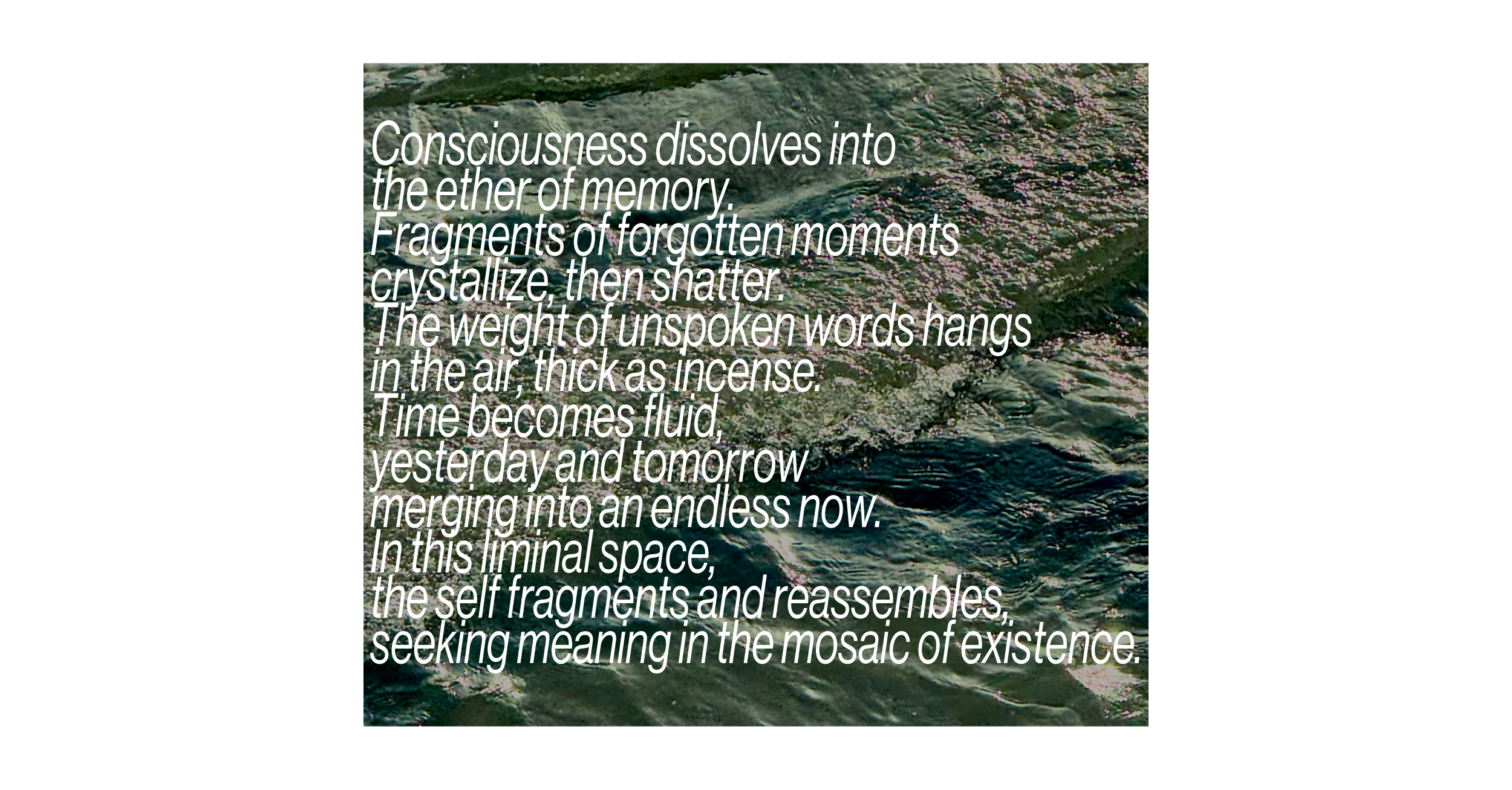「消えてなくなっちゃいたい。ねえ、わたしこの世界に必要ないみたいよ。」
テヨン
「どうしてそんなこと言うの。」
居なくならないでよ、ここに居てよ。ずっと隣に居てよ。
そうしてきみに縋ることしか出来ない僕でごめんね。
苦しみも悲しみも、僕の分まで背負おうとしてくれる君だから、きっと抱えきれなくて苦しくなってしまったんだね。
僕にはずっと君が必要で、君にはずっと僕が必要なんだ。
絶対離したりなんか、しないからね。
ただ静かに涙を流すきみの肩をぎゅっと抱き寄せて、大丈夫だからね、と声をかけることしか出来なかった。
ジャニ
時折、彼女はこうして“ 生への許諾” を求める。
誰かの『生きていて良いよ』が無ければ、自分は死ななきゃいけない。
どうして君がそうなってしまったのか、君が僕に教えてくれることは無い。僕はきみの苦しみさえ、知ることを許されない。
「この前約束した映画は一緒に見てくれないの? 」
君がいないと寂しいんだ。一人ぼっちで見る映画は、ポップコーンで胃もたれしちゃうしね。
君は自分が世界に必要ないなんて言うけれど、この世に本当に必要な人間なんかいるんだろうか?
そんな空想に思いを巡らせながら君を胸に引き寄せた。
ユウタ
「なあ。それ辞めや言うたよな、俺。」
ぴしゃり。
そんな慣用句が似合うくらい、自分でも思ったより冷たい声が出て驚いた。
ココ最近の彼女は酷い落ち込みようで、特に3 日前に『死にたい』と零してから日に日に窶れて、好きだったはずの彼女の面影が消えていっていた。
こわい。
彼女がそれを言葉に出す度、本当に死神がにじり寄ってくるみたいで怖かった。
真っ暗な部屋のベッドの上で項垂れる彼女は、本当に彼女なんだろうか。
皮膚を刺すような冷たい冬の空気はすぐそこに来ている。彼女を連れていかれないようにしなきゃ。まだこの世に引き止めなければいけない。
背後に寒気を感じる前に、部屋の電気を付けた。
ドヨン
ベランダでタバコを吸いながら彼女はそう気だるげに言った。
「それそのまま食べてみたら死ねるかもよ。」
「やだよ、不味いもん。」
「わがままだなあ。そんなんだからいつまでも死ねないんだよ。」
「でも一人ぼっちで死ぬのは寂しいじゃない? 」
はあ、とため息をひとつ吐いた。
僕らの関係は、友達でも恋人でもない、どっちつかずの間柄だった。
腐れ縁で、そのまま。いつの間にか紫煙を燻らせるようになって、それから彼女の銘柄は甘いものじゃなくなっていた。
「人様に迷惑だけは掛けるなよ。」
僕がきみの副流煙を吸うのは、きみをひとりにしないためだって、きみはいつになったら気付いてくれるんだ。
ジェヒョン
助けを求めるきみに、僕は口付けをすることしかできない。
きみをすくいあげる為の銀の糸に僕はなれない。
きみの涙を袖口で拭って、それからそんな忌々しい言葉を紡ぐ口先を塞いだ。聞きたくなかった。苦しいから。助けられない自分なんか、彼女にとってちっぽけなものだと、そう言われているみたいで。
そんなこと言わないで、も、僕の隣に居てよ、も違う気がして、軽く言うことが出来なくて、誤魔化すみたいに抱きしめるだけだった。
どうか僕が、きみの傷口を覆う包帯くらいにはなれますように。
「ねえ、ジェヒョンが殺してよ。そうしたらわたし、きっと幸せだから。」
ジョンウ
「な、んで。そんなこと。どうしたの? 何かあったの? 」
「何かなきゃだめなの? もう何がなんだか分からないの、疲れたの。終わりにしたいの。」
何時になく荒れた様子の彼女を見て、正直戸惑った。かわいらしくおひさまみたいに笑うきみしか知らなかった僕は、何も知らないバカだったみたいだ。
「……ごめんね、ジョンウは何も悪くないのに。ごめんね。」
「僕は良いから。だいじょうぶだよ、泣かないで。」
うぅ、と目を擦る君を見てると、いつものしゃんとした姿よりもずっと子供っぽくて愛おしい。君のいちばんに甘える人が、僕でよかった。
マーク
自分が本を読む隣で小さく丸くなった彼女がぽつりとそうこぼした。
「……そんな事ないよ。要るよ、絶対。」
下を向いたまま顔を上げない彼女の肩をさする。
「んー… 俺一人で洗濯できないし、ご飯も微妙だし、ほら。目玉焼きもやっと出来るようになったくらいだからさ……? 」
「……私の代わりはいっぱいいるじゃん。」
「誰かに何か言われたの? 」
言われたとしても、彼女がそういうことを俺に言わないのは分かっていた。そういう君だから好きなんだ。
「俺は好きだよ、全部。無くなったら嫌だな。」
だからお願いだ、死を希わないで。
ヘチャン
日付が変わる頃に帰宅した。
玄関に靴はあるのに電気が付いていなかったから、そんなことだろうなと思った。宵っ張りなきみが、もう寝ているなんて事は滅多にないのは分かっている。
疲れ果てた体を引き摺って、暗い水底みたいな寝室へと向かう。
「ただいま。」
さめざめと泣くきみの横に座って思いっきり寄りかかった。俺も泣いてしまえばよかったかな。
「なあ、おいしいワインもらったんだよ。飲まね? 」
アルコールで忘れられることなんかほんの少しだけなのは分かっている。
本当に神様がいるのなら、こんなに苦しまずに済んだはずなのに。
本当に俺たちのために血を流すくらい慈悲深い神なら、早く俺らを殺してくれよ。
ジェノ
「じゃあ俺と全部辞めちゃおうか? 」
まず退職届から書いて~ 、その次はどっか遠くにお引越しする? キャンピングカーに住むのも良いかもねえ、全部絵にかいた餅みたいな絵空事だけど、それで今きみの心が少しでも晴れるならそれで良いんじゃないかと思う。
「……そうする。」
「おー、じゃあ決まりだ。」
赤子をあやす様に自分の胸の中にきみを閉じ込めて背をさすった。
本当に君をどこかへ連れ出して、閉じ込めてしまえればどれだけ良いんだろうか。
このままずっと傍に置いておきたい。晴れることの無い欲望をぎゅっと押し込めるように、彼女を抱きしめる力を強めた。
ジェミン
空にとけた彼女の言葉と同時に、閉まりきらない蛇口から落ちた雫のシンクに落ちる音が聞こえた。
ああ、このまま彼女をここで殺して自分も死んでしまえば良いのか!
何ていい事を思いついたんだろう。ここで終わりにしてしまえば、大事な彼女がこれ以上傷付けられることも無い。無力な僕のせいで、傷だらけになる君をもう見なくてもいい。
「……一緒に死のうか? 」
否、と首を振る彼女の首に手をかけて押し倒す。
涙がこみ上げてくる。望んだはずなのに、どうして悲しいんだろう。息が上手くできなくて苦しい、僕の首は締められていないはずなのに。
手が震えて力が入らない。
上手に殺せなくてごめん、君を失うのが怖い僕でごめん。
ロンジュン
「はいはい、来月旅行行くんだろ? 」
ティッシュで彼女のぐしゃぐしゃになった顔を拭いてやる。遠慮なく泣き喚く彼女の世話を焼くのも悪くなかった。
「温泉楽しみにしてたじゃん。死んだら行けないけどいいの? 」
「よくない、けど……もう来月まで頑張れないよお~ 。」
できるできる、そうやって今までだって頑張れてたじゃん。
こうして涙を流すことで彼女は彼女なりに整理を付けてるんだろう。本当にダメな時はこんなふうに泣かないのを知っている。だから今は安心して鞭打っている。
「仕方ないなあ、今日は特別だからな。」
お風呂も入れてやるし髪も乾かしてやる。
俺がダメになった時、君がいつもそうしてくれるから。
チョンロ
何も言わずに隣にいてあげることしかできない。何を言っても、今君の心に俺の言葉が届くことはない。嗚咽をあげて泣く彼女を見るのは辛かった。自分の不甲斐なさばかり感じた。好きな人の1人も守れない自分に一体何ができるんだろう。その苦しさがきっと自分の十字架だ。悲しみを肩代わりすることは出来ないけれど、君を背負うことは出来る。
「……あんまり擦ると腫れるよ。」
冷やすタオルを持ってこないと。これじゃあ明日彼女がまた凹みそうだから。
「やだ、いかないで。」
指先に手をかけるだけで掴まない彼女が意地らしくて可愛かった。俺は掴んで欲しいのに。
「わかった、行かないよ。」
重かった空気はいつのまにか甘い匂いがし始めていた。
チソン
「ヌナ…… 僕、どうしたらいいですか。ヌナ、僕、ヌナに死んで欲しくないよ。」
僕のTシャツの裾を掴んで“ 死んでしまいたい” と訴えた彼女は泣きじゃくるばかりで答えてくれない。「どうして死にたいなんて。」
ずっと一緒にいたいね、先週そう言って笑ってたのはヌナじゃないか。
目の前の彼女は別の人みたいだ。どうしてそんなに悲しむの? ヌナが生きる理由は僕じゃダメだった?
色んな考えが頭を駆け巡るのに、唇が震えてひとつもちゃんと言葉にならない。
目の前の人が冷たくなるのを想像して怖くなった。
どうかまだ僕の前で、お願いだから。
君の手を握って祈る。
「僕はヌナのためならなんでも出来るから、だから死なないで。」
静かの海の叫び ( 2 0 2 2 .1 1 .0 6 ) 再録