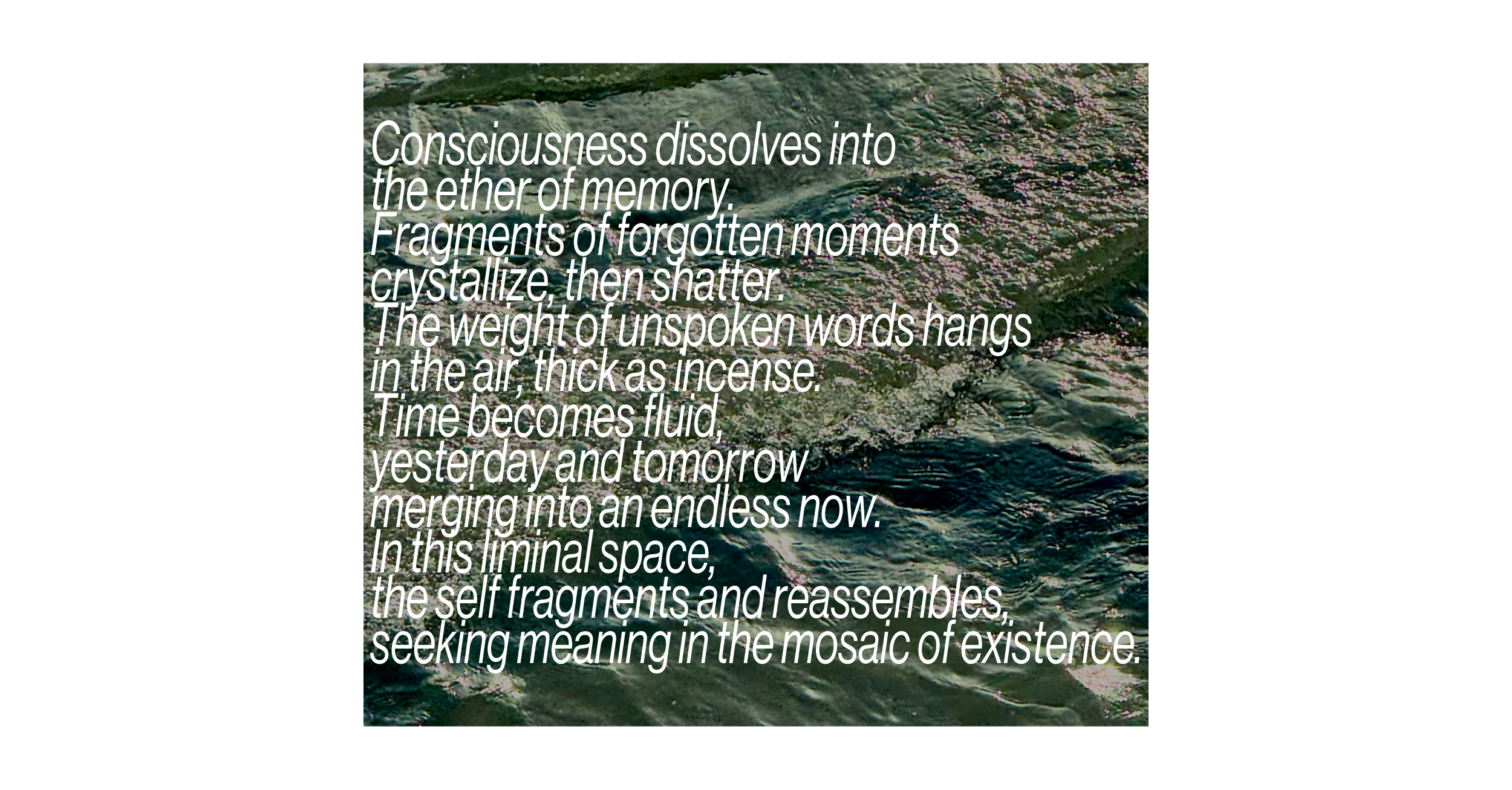優しい朝の陽の光が、本当にその姿なのかなんて誰にもわからない。優しげな顔をしていたってその実、誰かをいつか殺す強い熱波だということもあるのだ。
きみにもそんな一面があるんだろうか。
栗色の柔い髪を一筋掬って口づける。
だって、君の唇は許されていないから。
どうして僕ら、こんな二人になってしまったんだろう。どこで間違えてしまったんだろう。
「私って彼女じゃないよね。」
濡らしたタオルで彼女の汗を拭りながら、そう言われた。それは彼女にとって問いかけなのか確認なのか。
心地良いこの間柄に、一体どう名付けるのが正解なのか、その時すぐに答えが出せるほど器用な人間じゃなかった。
きっと、優しい人だったら、きっと。きっと。
少し考えてみたら、自分より彼女に相応しい人がいるんじゃないか、そう思った。明瞭に関係を見通す事も出来ずに勝手に未来を想像して、勝手に諦める自分なんかよりも、うつくしいきみに似合う人がどこかにいるんじゃないか。心の何処かでこれ以上の人に出会えない事はわかっているのに、それを掴む勇気がなかった。
次の朝、君が泣いていた事を本当は知っている。それを知らないことにして、少しでも君と過ごす時間を増やしたくて朝食を作った。君は僕が朝ごはんを作るのを嫌がるのに。
二人して飲めないカフェインが、この関係がママゴトで有ることを知らしめていた。