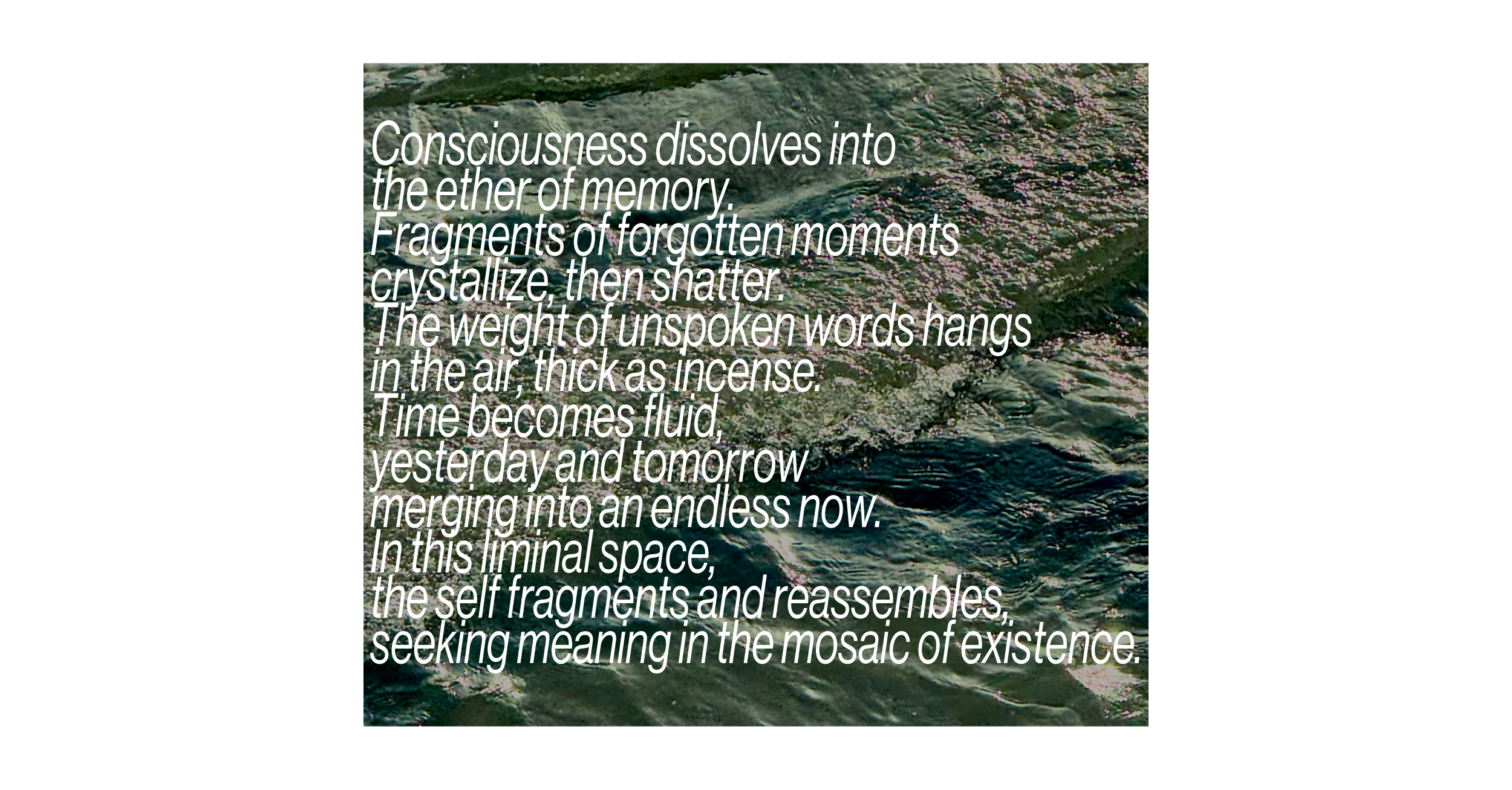夕食はまだだったけれど、食欲がないからと伝えるとさっとスープを出してくれた。本当に生活スキルが高いなあと感心する。
「ちゃんとご飯食べてるの?」
「うーん、あんまり。忙しくって。」
「食べないと夏バテするぞ?」
鍋を洗いながら背中越しに言葉を投げてよこす君に、私は眉をさげることしか出来ない。
忙しいだけじゃない。きみのせいで。
自棄になるのは良くないと、分かっている。
そうだからこうなっているのだ。
洗い場で皿を拭く彼の横に並んで可愛らしいマグを濯いだ。パステルな青とピンクで、ベージュのテディベアのカップルが片割れずつ描かれている。“アベック”の時代を彷彿とさせるような絵柄だったが、そのレトロさがセンスの良い彼によく似合っていた。この子たちには本当の持ち主がいるんだろうか、私以外に、この桃色に口付けた人がいるんだろうか。
流れていく泡をぼんやりと目で追った。おい、と水を止められて、ようやくもうそれがすっかり消え去っていた事に気付く。
眉を下げて心配そうな、きゅるりとした瞳がこちらを見つめていた。
「お風呂沸いてるから。もう入ってきな。」
「うん。ごめん、なんか。」
惨めだった。幸せそうな男に、一体なにが分かるっていうの。いつかこの部屋に、あのブサイクなクマはぬいぐるみになって置かれるんだろう。
へらり、と笑ってごまかしてしまう自分の途方も無い浅ましさに嫌気が差す。
キッチンタオルで手を雑に拭ったって曇った心のガラスは拭けない事はわかっていた。分かっていても、そうしてしまう。
「……今日は、気使わなくていいからさ。」
くるりと背を返しかけたときに掛けられた言葉の意味を咄嗟に理解出来ずに首を傾げる。
「疲れてるのに、無理させられない。」
「あ、ああ。別に良いよ、どうせ布団に入ったってろくに眠れないし。」
私を呼んだのだって、そういう用事でしょう?とまでは言わなかった。
流石の私でも、そこまでの無情さは持ち合わせていない。
眠れないのは本当だった。だから、気絶するほどのセックスをした方が余程疲れが取れるかもしれない、と思った。
「そっちこそ、今日は気使わなくていいから。それとも普通に早く寝たかった?」
「いや、いや違う、くはないけど。」
くく、と喉を鳴らして笑う。何度も体を重ねているくせに、やけに初心な反応を返すものだから面白くて時折からかってしまう。
「違くはないけど?」
「あーもう!元気なら早くシャワー浴びて!」
元気なのはそっちでしょ、と意味深長な言葉を付け足してから脱衣所に姿を隠した。
「……なんだよ、もう。」
きみが顔を歪めたすがたは、私には見えるはずもない。