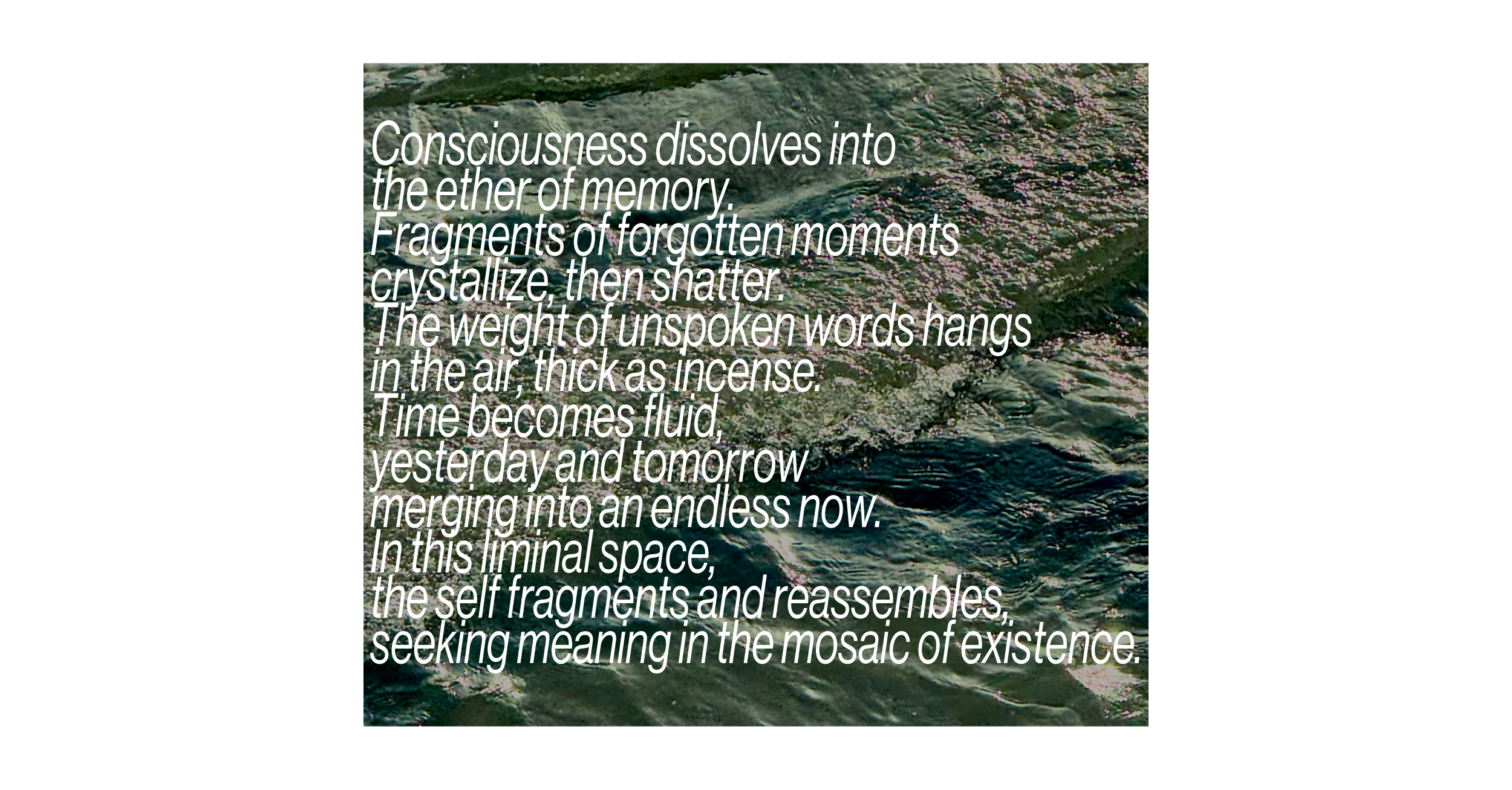珍しく定時にタイムカードを押せた私はごきげんにダイアナのパンプスで街へ出た。
いつの間にか冷たい秋の風が吹き始めていて、そろそろ並木道も衣替えの季節だろうと感じさせる。
勤務先から3駅、乗り換えてまた3駅。降りたのは都会の喧騒を忘れさせてくれる少しお洒落なバル街だ。ガス灯がオレンジ色のロマンを光らせて、駅前には待ち合わせも多い。
周りをひとしきり眺めたあと、自分の爪先を見つめる。3日前の休みに新調したツイード調のネイルアートは一足先に冬を宿していた。
この街も冬にはイルミネーションをやるそうだ。きっとクリスマスのカップルで溢れんばかりの盛況を見せるのだろう。
まだ遠く感じる冬の景色を思い浮かべ、幸せの色に染まる世界を感じる。
「ごめん、待たせた?」
待ち望んだ声に自然と笑みが浮かんでしまう。こんな自分が気持ち悪いはずなのに、どこか浮かれ調子なのはきっと彼が魔法使いだからだ。
ああ、ことしはきちんと私も幸せの色に染まれるだろうか。
「ううん、全然。」
「寒かっただろ?外で待ってなくても良かったのに。」
「いいの、外で待つのも楽しいから。」
風邪引くなよ、と小言を言いながら不思議そうな顔をする君の手を奪う。
皆が誰かの為に、誰かを思って待っている。
同じ時間、違う人生。
夕暮れの色と、待ち人を迎えた人の表情を覗き見るのが好きだった。
すれ違った知らぬ人の幸せを願う事が出来る自分が幸せだった。
たったひとつ、恋を得ただけで世界が変わるなんて陳腐な事がある訳がない。
今だって、心の半分くらいはクリスマスまで隣に居れるわけが無い、私なんか幸せになろうなんて烏滸がましい、そんなふうに思っている。ここに並んでいる人達とわたしは多分生産ロットか何かが違うんだろう、そう思っている。きっと私は彼らみたいに、本当に幸せに待ち人を迎えることは一生出来ず、一生待ち続けることになる人生に怯えて息をし続ける。
けれど今隣で楽しげに予約したレストランの看板メニューを語るきみが嘘だなんて、とても思えないのだ。この手の温もりが嘘だなんて自分にだって言い聞かせられない。
彼に私の全ては話さなかった。ただ、好きであること、それがあればいいと思った。
少しずつ教えて欲しいなんて甘言は無かった事にして、ただわざと隠すことを辞めにした。
だから彼は何も知らない。知らないから笑っているのかもしれないし、知らない事を分かった上で笑ってくれているのかもしれない。
あの日傾けた赤ワインとは似つかない、豊かで香り高い、実りの象徴としての葡萄の似合うグラスを交わした。
今日あったこと、次はどんなところに行きたい、こんなものが食べたい(彼は案外グルメだ)、私からの話題は専らお酒の話ばかりだったように思うが、それでも楽しく話は弾み、いつの間にかこの店のセールスポイントである子牛のフィレステーキは食べ切っていた。
目の前でソムリエが食後におすすめだという白ワインを注いでいく。こってり甘いがしつこくなく品のあるもので、確かに良い。
このワイン、と口を開いたところで、すっかり彼とハモってしまったことに気づく。2人で顔を見合わせて笑ってしまった。気取った店内に流れるクラシックだかジャズだかとかちょっと離れた朗らかなこの人の笑い方が好きだ。
先に話せと目線で促され、言葉を続けた。
「いや、大したことじゃないんだけどね。」
「うん?」
「このワインの味、少しドヨンみたい、と思ったの。」
「俺?」
「うん。似てるよ。」
特に冬のころこういう感じだよ、と伝えると訝しげにこちらを見返してくるものだから、面白くって仕方がなかった。
一通りからかった後、いつの間にか済まされていたお会計にまた彼のさり気ない“慣れた感じ”がしてときめいたんだか腹が立ったんだかよく分からない感情になったまま外へ出た。
「……この後、どうする?」
「どうして欲しい?」
「いや、無理強いは出来ないし、名前が決めなよ。」
「私はドヨンが好きなようにするよ。」
「そう言われるのがいちばん困るって分かってるくせに。」
ふふ、と笑うと、行きは私から取った手が取られ、駅の方へと歩を進められていく。
少し酔ったのか、ちょっぴりとろんとした目が歳下みたいに見えて可愛らしかった。
「ドヨンの家に帰るの?」
「そのつもり、だけど。」
「なら歯ブラシ買いたいからコンビニに寄ってくれない?」
「うちにストックあるよ。」
「お、気が利くじゃん。」
最初から名前より利いてる、とふざけ合っているうちに、電車が来て2人で乗り込んだ。
終電と帰宅ラッシュの狭間の車内は人もまばらで、ぽつりぽつりと帰路に着く人々がいるだけだ。なんだか2人で年甲斐もなくうるさくするのは憚られる気がして、静かに繋いだ手は上手く隠して立っていた。
ドヨンは夏に住んでいたマンションは引き払い、秋へ移り変わると同時に西側の閑静な住宅街にある低層マンションに移っていた。
前の家は青い光がよく入る部屋で私も気に入っていたが、今度の家は緑がよく見える大きな窓があるという。
知り合いが設計したとか何とか言っていた気もするが、訪れるのはなんだかんだ今日が初めてだった。
バル街から4駅先のその街はそこそこ家賃が高いはずだが、一体ドヨンがなんの仕事をしているのか、前にいつか聞いたけれど聞き流してしまってから改めて聞くのもおかしい気がして知らなかった。
繋いだ手を見ながら夜の道を2人で進む。私の手首まで簡単に包む彼の手のひらを見て、このあと起こるであろう情事まで想像してしまい勝手に恥ずかしくなる。
そう、事もあろうかあんなに爛れた関係だったと言うのに!今日という今日まで夜を越して過ごすことが無かった。何度かこうしてディナーはすれど、ここ1ヶ月程は駅まで丁寧に送られて家に返されることが多かったのだ。
彼なりのけじめなのだろう、とは思っていたけれど、散々セックスばかりしてきたというのにお預けされるのもなんだかなあとは思う。セルフ禁欲プレイを布かれているのだろうか。
1度下世話な事を考え始めると取り留めもなくこぼれて行ってしまって、自分の堪え性のなさに驚くばかりである。
「ドヨンの家、楽しみだな。」
「え?」
「何動揺してるの、普通に引っ越してから初めて行くからだよ。」
ケラケラと私を肩で小突く彼も、そこそこ同じ程度の品の無いことを考えていたらしい。
“家”“楽しみ”という単語でここまで動揺できるのは男子高校生くらいのものだと思っていたけれど、中々初な人である。
ぽつりぽつりと古びた街頭が照らすアスファルトに、ひとさじの緊張が混ぜられる。
足を止めた建物は黒を基調とした如何にもお高そうなマンションだった。
「ここ。」
「おー、デカイね。」
まあ稼いでるからね、とドヤ顔をしてオートロックを解除する様子が、なんだか新しい玩具を自慢する子供みたいで可愛く思えた。
「何階?」
「1階、庭付き。」
「ええ、管理大変じゃない?」
「いや、案外楽しくやれそうだよ。」
「ドヨン何かしらの面倒見ないと生きていけないもんね。」
「認めるけど何か悪意を感じる言い方だな。」
「だって込めてるもん。」
黒い質の良さそうな石で出来た通路の脇には白い軽石が詰められていた。角部屋らしく、日当たりも良いから洗濯物もよく乾くし〜と主婦みたいな物件感を述べる彼が面白くて笑うとぷくっと頬を膨らませていた。可愛い人、歳上だけど。
最近彼の方が4つも歳上だったという事が発覚して驚いた。付き合い始めるまでまともに年齢の確認もせずにいたのがおかしな話と言われればそうなのだが、歳上だと分かったところで今まで取ってきた舐めた態度を改めるのも変かと思って彼をおちょくり続けている。なんだかんだ満更じゃ無さそうにニコニコ笑っているので、彼は真性のマゾヒストかもしれない。
『はじめてのお泊まり』なんて学生カップルのようなシチュエーションに失笑してしまうが、この珍妙な緊張感と赤く染った彼の耳はまさにそれとしか言いようがなかった。
場所が変わっただけで全くもってはじめてなんかでは無いのだが、ひと月も空いていると不思議と緊張するものである。
「……お邪魔します。」
「どうぞ。」
用意されたスリッパはどう考えても彼が買うには可愛すぎるお揃いのウサギが刺繍されたもので、思いっきり吹き出してしまう。
「なにこれ、可愛すぎじゃない?」
「いや!俺が買ったんじゃなくて!引越し祝いに押し付けられたの!」
「なに?同棲でも始めると思われてるの?」
笑いすぎて頬の筋肉が吊りそうになっているが、同棲の単語を出した途端分かりやすくしどろもどろになる彼がもっとおかしくて笑いが止まらない。今日の彼は割と総じて挙動がおかしくて、それでいてやけに気合いが入っていた。
家に誘うから緊張しているのかと思ったけど、何となくこれで察しもついたというものだ。
「一緒に住んだあげようか?こんな広かったら寂しいでしょ?」
室内もモノトーンと柔らかい木材の温度が程よく混ざりあっていて、前の家とはまた違うタイプのオシャレさを感じる。
高級感のある玄関から、長い廊下と、それからいくつ部屋があるのだろう。どう考えても一人暮らしには多すぎる部屋数だ。
「……もっとちゃんとムードある感じで言いたかったのに。とりあえずリビングまで行こう、いいシャンパンまで用意したのに……。」
萎れたうさぎの耳が見える。ちょっと可哀想なことをしたかとも思ったけれど、彼が私と一緒に住むことを考えてくれたと思うと嬉しくてスキップまで出来そうだ。
「わたしモエのロゼシャンパンが1番好き。」
「今日はもっといいやつだよ。」
「ほんと?嬉しい。」
「名前が喜んでくれるなら良かったよ。」
リビング脇の大きな窓からは庭が見え、植木が揺らす葉や風の音に自然と触れることが出来る。
荷物を置いて、アイランドキッチンに立った彼をソファから眺めた。
見ているだけじゃ寂しくなって、ウサギのついたスリッパをパタパタ鳴らしながらキッチンに向かった。
「ドヨン。」
「うわ、急に抱きついたら危ないって。」
「ただいま。」
「?おかえり。」
わたしの帰り道の行く先に、誰かが待っててくれるようになる。
こうして彼がキッチンで温かい料理を作って待っていてくれる日も、私が彼のいるところに立って、いつの日にかもしかしたら子供と彼の帰りを迎える日も来るのかもしれない。
「あごめん、その下の棚からグラス取って。」
「はいはい、結局ムードないじゃん。」
「ムードなんか作らなくても俺と住んでくれるつもりなんでしょ?」
「……まあ住んであげないこともないけど?」
「素直に住みたいって言えばいいのに。」
「それはなんか癪なの!」
多分これから先もずっと、生きるのは辛くて、苦しくて、全然幸せなんか見つからない。
きみと一緒なら少しだけ楽で、もう少しだけきみのために生きていようと、そう思えた。
もう少しだけ手を取って、きみの肩を借りて、こうして笑っていられたらいいな。
そうしたらたぶんいつか、それに幸せという名前を付けられるから。