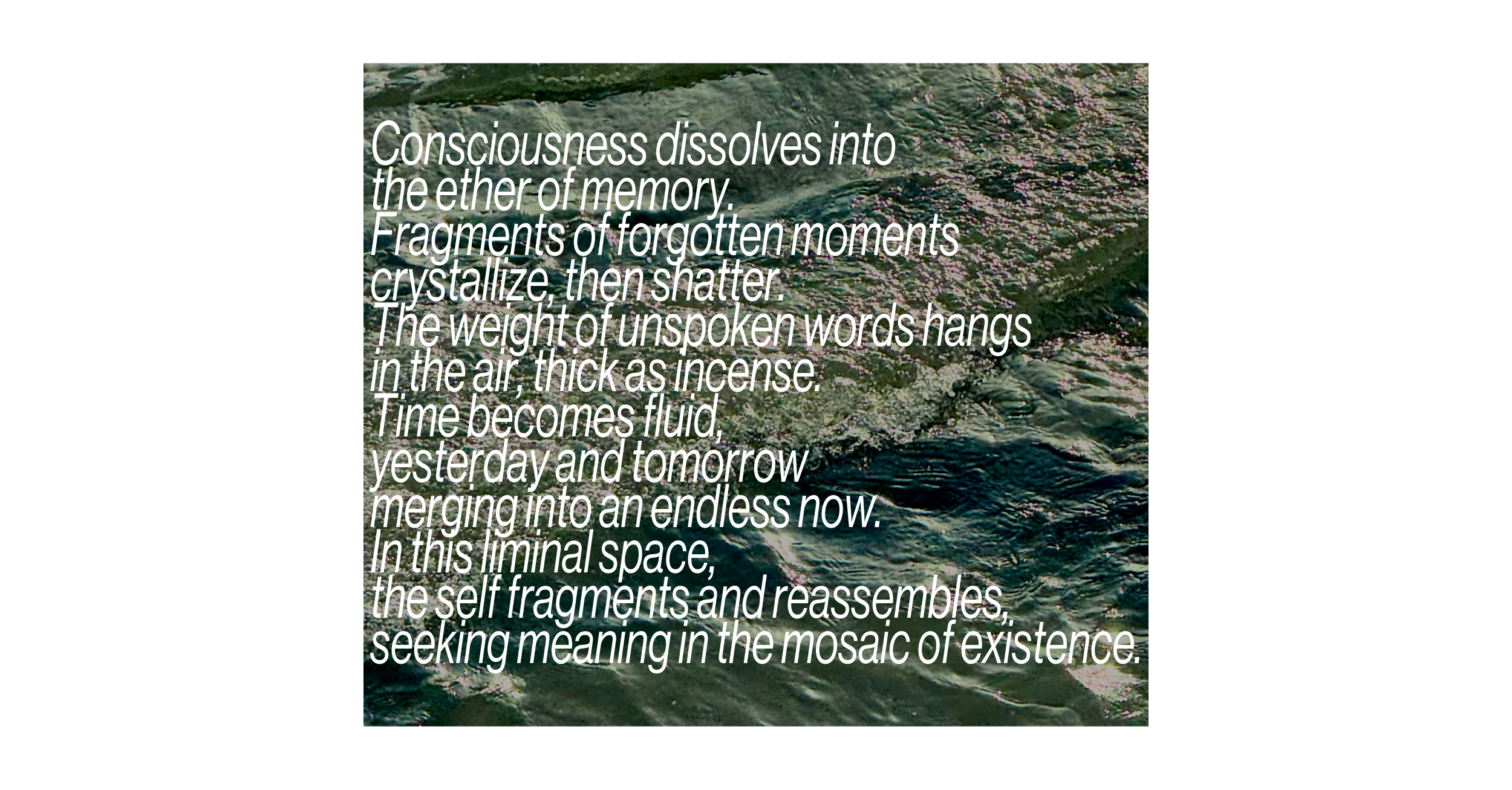「……え、あ、あはは。いや知ってたけど?」
「そ?ならいいけど。あんなジェミンと距離近いとそのうち先輩に怒られるよー?」
「分かってるって。」
昼下がり、秋の風と陽が心地よくてまさに運動日和だった。
本当は知らない。全然知らない。聞いたことも素振りもない。そもそも四六時中ほとんど私と居たのに、そんな先輩とお付き合いする暇なんてどこにもあるはずない。なのにどうして?
水族館も美術館も、ふたりで見た星空も、もしかして全部先輩との為の予行練習だったの?私は練習台?先輩と仲が良くて趣味趣向が似てたから、手近でちょうど良かった私を利用してたってことなの?
彼と出会って一緒に時間を過ごすようになってからもう半年経っていて、青々としていた木々もいつの間にか色とりどりの葉を付け、また散り始めていた。
大学までの銀杏並木をひとりで歩いたのはいつぶりだろうか。いつも乗っていた8:46分着の電車も飛ばした。
どうしても顔を合わせられる気がしなくて、申し訳ないけどいつもの待ち合わせ場所とは違う駅の出口から出て、わざと遠回りしている。そんなことしたって授業で会っちゃうのに。
それまで毎日となりを歩いていた人が、他の誰かの隣を歩くことになるなんて、考えもしていなかった。私たちはお互い好き合っていて、ただモラトリアムを楽しんでいるだけ。そう思い込んでいた私がバカだったのかもしれない。彼だってあんなにイケメンなんだから、私の数倍は過去の恋愛経験も豊富だろう。きっと私ひとり騙すことくらい造作もない。
そう言う考えがグルグル回るのに、今までのひとつひとつの思い出があまりにも綺麗で頭から離れてくれそうになかった。あの時間のすべてが嘘だなんて到底受け入れられない。暫くアップルミュージックのおすすめが失恋プレイリストになりそう。
校門に入ってしばらく歩くと、授業の棟の前に不機嫌そうにスマホをいじるジェミンが居る。何で苛ついてるの?私が居なくてもなんとも思わないくせに。それとも不都合なことが露見したのに気付いて腹を立ててるんだろうか。
とにかくどう回避しようか。取り敢えずバレないように顔は伏せたほうが良いだろうと思って、彼と出かけたときに買った赤いマフラーで口元を覆った。それすら憎いはずなのに、まだ彼の選んだマフラーに埋もれることが出来ることへの嬉しさがまだ残っている。残滓が苦い。
他の棟から何とか迂回して、隣が誰かを確認するまでもなく適当に席についた。
「あれ?今日ジェミナと一緒じゃないんだ?」
げ、と言わなかった自分を褒めちぎりたい。だって、隣の席はかの遊び人で高名なイ・ドンヒョク氏だ。妙に距離が近い。パーソナルスペースが存在してないのかコイツ?
「なに、喧嘩したの?」
ニタニタと笑って誂う気満々と言ったご様子。応じたら負けだし、そもそも私は彼と面識なんてほとんど無いはず。それなのにこんな失恋ホヤホヤの姿を晒す訳にいかない。彼に知られたら次の日には学年中から勘違い女のレッテルを貼られることになるかもしれないし。
「あー名前ちゃんつまんないの。ジェミンも何が楽しいんだか。」
誤魔化す為に走らせていたペンが止まってしまった。
あ、と思った時にはもう遅い。彼の策略にまんまと嵌ってしまった。
「お、図星?」
「やめてください、私あなたのこと知りません。」
「傷つくなあ、俺だよ俺?ジェミンと一緒だった時何回か話したじゃん〜覚えてるくせに。ごまかし方下手すぎ。」
「うっ。」
「しょうがないなあ、恋愛マスタードンヒョクが相談乗ろうか?名前ちゃん可愛いし♡」
それから授業中なのにドンヒョクくんに洗いざらい吐かされた。なんなら私はドンヒョクくんに知ってたんでしょ?って逆ギレまでかました。厄介女過ぎる。
だけど流石のプレイボーイ。女の子の癇癪なんて慣れっこなのかするっと交わして飄々と話を聞いてくれる。体目当てで女の子口説いて回ってるにしろ、面倒くさい「女の子」という生き物の相手ができて偉いなあ、と思った。
授業が終わって開放されるかと思いきや何故か時間割まで把握されており次のコマもドンヒョクくんと受ける事になってしまった。ジェミンの時間割知ってるから必然的に知ってるよ、とのことだ。
「名前ちゃん的にも好都合じゃないの?」
言い返せなかった。
それに彼の存在感がデカすぎるお陰でジェミンを意識する事もなく、少し呼吸がしやすくなった気すらする。
お昼ご飯も誘って貰って、胃になにか入る気がしないからと断ったらご丁寧にゼリーまで買ってきて一緒にコンビニご飯にしてくれた。女の子が続々落ちていくのも納得の域。
こうやってどこまでも斜に構えて考えてるからジェミンにも捨てられたんだろうけど。
「これからどうしよう、全部ジェミンと同じ授業なんだよ……。」
「必修は最悪俺の隣に座ればいいけど、アイツマジで何考えてんの……。」
「そんなの私が聞きたいよ。」
そこそこ気分も戻ってきて、ドンヒョクくんにお礼を言って連絡先を交換したあと、なんとか避けて三限を乗り越えそろそろ帰ろうか、そう思って朝の電車ぶりに携帯を開いた。
「な、に。これ……。」
そこにあったのは夥しい数の着信とカトク。もはや狂気すら感じる量。
どうしたの、大丈夫?と言った心配の類から時間が経つにつれ『なんでドンヒョクといるの』『俺の事嫌になった?』『もう会えないの?』など、まるでメンヘラ彼女かのような文面が軽く100件程度届いている。ずっと私たちの事を見ていたようで、なんなら『ドンヒョクの連絡先なんて危ないからダメ!』とか送られてきていた。ストーカー?
ちなみに最後のメッセージは『駅で待ってる。』に、可愛らしい猫の『まってます!』というスタンプ。
ちなみにナ・ジェミンの奇行に慣れた私はびっくりしつつもメッセージを追いながら歩いていたので、地下鉄の駅の出口の前までもう来てしまっている。どうしよう。
ここで引き返して隣駅まで歩いたとして、明日も明後日も変わらず私の帰りの時間はバレている。最後のコマに今日みたいに必ずしも知り合いがいる訳じゃない。いつか捕まるのは明白だ。
だったらもう、潔く今日さようならを伝えた方が良いんじゃないか。
そう思いながら一段一段階段を降りる。ヒールの音がやけに響いて、世界でひとりぼっちみたいな感じだ。
改札前、朝と同じようにスマホをいじるジェミンを見つけた。改めて見ると足も長いし立ってるだけで絵になるって凄い。私がベタ惚れみたいで嫌だけど、こんな格好いい人の隣にずっと居たのかと思うとむしろ怖くなってきた。
「あ。」
「……ごめんなさい。」
なんで謝るの?別に怒ってないって、って言うけど、目が笑ってないじゃない!
「名前が朝来なくて、なんかあったんじゃないかって心配した。」
「うん、でも、」
はじめて呼び捨てで呼ばれた名前に今まで繋いだことの無かった手も、こんな時に限って。せっかくの恋人らしいシチュエーションをこんな気持ちで迎えたくなかった。
喉から出かかった別れの言葉も、吸い取られてしまったみたいに何も出てこない。
やっぱり私ダメだ。
これじゃあドンヒョクくんに口説かれてる女の子たちと何ら変わらない、ただの勘違い女じゃないか。
電車に乗ってもまだ繋がれたままの手を恨めしく眺めて、涙がせり上がってくるのも気付かないふりをした。私が下を向いている限り彼に気付かれることはないだろう。ただ私がひとりで恋をして、ひとりで泣いているだけだ。虚しい関係で、勝手に失恋してるだけ。彼が知る必要もない。
「ねえ。」
下を向いたまま、震えそうな声と溢れそうな涙を必死に押さえ込んで彼に声を掛ける。
「これからも私と友達で居てくれるよね?」
「なに、急にどうしたの。」
彼は今どんな顔をしているんだろう。恋人みたいな事をして、友達だよね?と問いかけられた君は戸惑っているだろうか。それとも普通な顔をして、何とも思ってないかもね。
「いいから、答えて。」
「え?うん、ずっと隣に居るよ。」
はは、嘘つき。
気づいたら降車駅だった。そう笑って降りた私に、ジェミンは気付いただろうか。
──それから、1ヶ月が経った今日。
なんとかドンヒョクくんの協力も有り、友達には愚痴りまくってジェミンから距離を置くことに成功した。
時々ジェミンが何か言いたげな目を向けてくるけど、あの日言外にあった『友達ならこんなことしないよね?』を察しているのか直接話しかけてくる事もカトクを送ってくる事も無かった。
それで今日はサークルの飲み会だった。ついでに例の先輩の誕生日会も兼ねている。ジェミンと距離を置いてからサークルでの友達も増えた。入りたてはみんなジェミンに首ったけだったけど、秋にもなればそれなりにボルテージは下がっていて、他に彼氏が出来た子も多かったから大分雰囲気も良くなっていた。だから、今日は憂さ晴らしくらいの気分で来たのに。
「あの、ちょっと。」
「え?何?」
膝を触ってくる2個上の先輩にうんざりする。ここお触りOKのパブじゃないんだけどなあ。
うんざりしてジェミンに視線をやると、噂通りに先輩の隣に腰を下ろしていた。なーんだ、やっぱり本当だったんだ。
あんな事があった後も、変わらず私はジェミンを目で追ってしまう、恋する乙女だ。そのうちそれにも飽きるだろうと思って、無理に諦めることを諦めた。
そもそも手を離したのは私で、彼らの関係にとやかく言う権利は無い。直接確かめるまでの勇気も無くバイバイしたのは、結局私は私の方が大事だったということの裏返しでもある。傷付くのが嫌だっただけ。ただそれだけの意気地無しが彼の隣に立つなんてきっと許されない。
「そう言えば名前ちゃんジェミンくん取られて残念だったね、何かあったの?」
「いや、別に最初から付き合ってないですし。」
え、そうなの?じゃあ最初から狙っとけばよかった〜とほろ酔いテンションで抱きつこうとしてくる先輩を軽く避けて、ちょっとお手洗い行ってきますね、と席を立った。
まあ、そんなこんな言ったって、未だにジェミンとの思い出を振り返ってしまったりあんな感じなことを言われると胸は痛むのだ。全然引きずってる。
急いで個室に入りたかったのに、生憎先客がいた。知らない人の前では泣きたくない。
いつまでもトイレで何してんだよ、行き場のない怒りを知らない人にぶち当てて、それが情けなくて余計に涙が零れそうになる。
そんな時に限って、後ろから丁度ジェミンの声がした。先輩の甲高い声と一緒だ。
ただでさえ沈んでいた私の心を突き落とすには何とも最適な一手。
丁度よく出た前の人の顔もよく見ず、最大限のスピードで個室に突っ込んだ。
みじめだ。てかなんでトイレにまで付いていくの?意味わかんない。
せっかくめかしこんで付けたマツエクも、泣いてこすって何本も落ちてしまった。
あーあ、なにやってるんだろう。
勝手に勘違いした女が飲み会に来て勝手に見せつけられてショック受けてトイレで号泣。ジェミンからしたら甚だしい迷惑で、私だって自分にこんな感情があると思ってなかったから理性はずっと困惑している。
コンコン、というノックの音で、自分が真っ先に物理的に与えていた損害を思い出し急いで顔面をどうにか工面した。
取り敢えずここを出たら荷物を持って外に出よう。きっと戻ったところでジェミンの顔を見る度辛い気持ちになるだけだ。
戸を開けて俯いたまま早口に謝って店内をガツガツと歩いた。いつからかジェミンに近づきたくて履き始めた7.5センチヒールのパンプスは未だに靴擦れしてじんじん痛む。
宴会が執り行われていた小上がりの個室の入口にまとめられた荷物の山から自分のバッグを見つけ、適当な人に適当な枚数のお札を預けた。
時刻は午後9時。
ジェミンの彼女はヴィトン、私のマイケルコースなんか追いつけない。
もうたぶん、頬を涙が伝ってるだろう。
店を出る時に、彼女と2人で立っているジェミンの顔が見えた。目が合ったけど、知らんぷりをしてそのまま近くの路地裏に駆け込む。
暗くて汚いそこは、いつもだったら絶対立ち入らない世界だ。
しゃがみこむといらなくなった酒瓶やビリビリになった詐欺広告が見えた。
私も彼らと一緒か。ジェミンにとって、もういらない存在。なあなあで続けたテニスももうやめ時かもしれない。
あーあ、もうやけくそだ。どうせここで泣いたってただの酔っ払いにしか見えない。何もかも好都合だ。
そう思ってわんわん泣いた。どうせ誰にも聞こえやしない。そもそも私のことを聞いてくれる人なんていないし。
「いた。」
もう全部どうでも良くて、何かを見ることも諦めて思いっきり泣いていた。
あの日と同じ、ベリーの香水だった。
「じぇみん、」
ああ、鼻水と涙でぐしゃぐしゃなのに。
せっかくしてきたオシャレもメイクも見てくれなかったくせに。遅い。もう全部台無しになったあとだよ。
「ダメじゃん、こんなとこ居たら。」
「ジェミンには関係ないじゃん。」
立てるように貸してくれた手も、拭きな〜って差し出してくれるハンカチも退けて、路上で貰った風俗の勧誘のティッシュを使った。
「関係あるよ、名前ちゃんは大事な人だから。」
「もっとだいじな人がいるでしょ。その人はいいの?」
私なんかに構ってたら怒られちゃうよ、涙と鼻声の隙間から嘲笑って見せる。
そしたらジェミンは溜息をついて、私の肩に掛けてくれたジャケットを寄せた。
「おんなのこってね、すぐ勘違いしちゃうからそういう事はしない方がいいんだよ。」
「ちょっと黙って。」
誤魔化すように目元を強く擦っていた手を止められて、ゆっくり私の頬を包んだジェミンの手が、親指が涙を掬って行く。
その度にまた新しい雫が伝ってしまう。
「……なんでそういうことするの、」
どうしようもなく、胸が痛い。苦しい。息が詰まって、うまく呼吸ができない。
ジェミンとの距離も、優しさも、叶わない願いも心の中で全部ごちゃまぜになって喉を詰まらせている。
「なんでっ、なんで、やさしくするの……ジェミンのこと嫌いになりたいのに、もう見たくないのになんで、」
不安だったね、大丈夫だよ。そう言って私の頭を撫でながら抱きしめたジェミンが分からなくて、私は彼の胸板を殴ることしかできない。1ミリも響いてなさそうだけど。
思いのほか強く抱き寄せてくる腕の力が強くて、脱出もできない。腕の中にいる間も先輩がチラつく。あの人もこの中にいたんだ。気持ち悪い。
「こんなことするのは名前にだけだよ、あの人とは何もないから。」
「え?」
ぴた、と驚いて動きを止めた私に、猛禽類かのような攻勢を見せるジェミン。あっという間にまた顔を捕らえられてジェミンの方を見せられる。目が離せない。こんなときだけ呼び捨てするのも、ずるい。
「何も無い。」
「でも!」
「全部うわさだよ、あの人は俺の事気に入ってたみたいだけど、こんなこともあんなことも、名前にしかしてない。」
そんなはず、無い。だってみんな言ってたよ。
子供みたいな駄々を捏ねて、でもジェミンは離してくれなくて。
それどころか一緒に出かけた時の思い出まで話してきた。実はプラネタリウムでずっと君の顔を眺めてた、水族館のイルカショーで水を掛けられた君がかわいくてしょうがなかった、ラッコのお揃いのキーホルダーは無くしたくなくて玄関に飾ってる、付けられなくてごめんね、とか。
「ね、俺はずっと名前ちゃんの事しか見てないよ」
真っ黒なジェミンの目が、路地裏の暗闇と重なって少し怖い。この人、こんなひとだったっけ。吸い込まれるみたいにずっと目を合わせたままの時間と、夜みたいな彼の黒い髪が顔にかかる。
「逃げるなら今だよ。」
「……にがしてくれるの?」
その時路地裏に響いたもうひとつのヒールの音。
振り向こうとしたけど生憎両手で私の頬をホールドしている彼に拒まれてしまった。
横目で見た路地の向こうに先輩と人の減った通りが見えた。
不安を湛えた目でジェミンを見る。
「今からキスするから、嫌だったら突き放して。」
「え?」
私が拒めないの知ってるくせに。
重なったくちびる。合わせるだけだったそれは段々と割り込んできて、息が上手くいかない。
途中で目を開けたら目線がかち合った後、ジェミンは先輩の方を見ていた。まるで見せつけてるみたいだ。なんだかいたたまれなくて私はまた直ぐに目を閉じた。
暫くしてまたヒールの音が聞こえて、そのあと少ししてからやっと長いフレンチ・キスが終わりを告げた。
「……まだ、聞いてないんだけど。」
私の涙の跡を撫でるジェミンに俯いたまま問いかける。
一瞬逡巡したあと、直ぐになんの事か察したようで。
「そんなの後でい〜っぱい聞かせてあげるのに。」
「いま言って欲しいの。」
好きだよ。初めて会った時から、君のこと好きなんだ。
居酒屋から漏れる歓声に混じったBGMが私たちのことを歌っているようだった。
また重ねるだけのキスが振ってきて、それから彼がやっと一緒になれたね、そう言った。
ちょっとずつペースが上がってきて、食むようにしてお互いの唾液を交換する。
路上でこんなことするなんてはしたないし迷惑だ、でも誰も見てるわけないじゃないか、色んな考えが浮かんでは消える。段々と頭が白くなって楽しくなってきて、最後には全部どうでもよくなった。
「ね、明日ふたりとも一限だよ。」
「じゃあふたりで昼まで寝ようよ。」
指を絡ませながら額をこつんと重ねてお互いの肌のつめたさで遊ぶ。頬だけが熱くなっていてアンバランスだな、と思った。
「もう戻れないね、どうする?」
そうやって悪戯に笑うジェミンを月のあかりがあやしく照らす。
「分かってるくせに。」
「うん、分かってるよ。」
彼とのキスは蜂蜜みたいな味がする。あまくて、あまくて、溶けて消えてしまいそう。