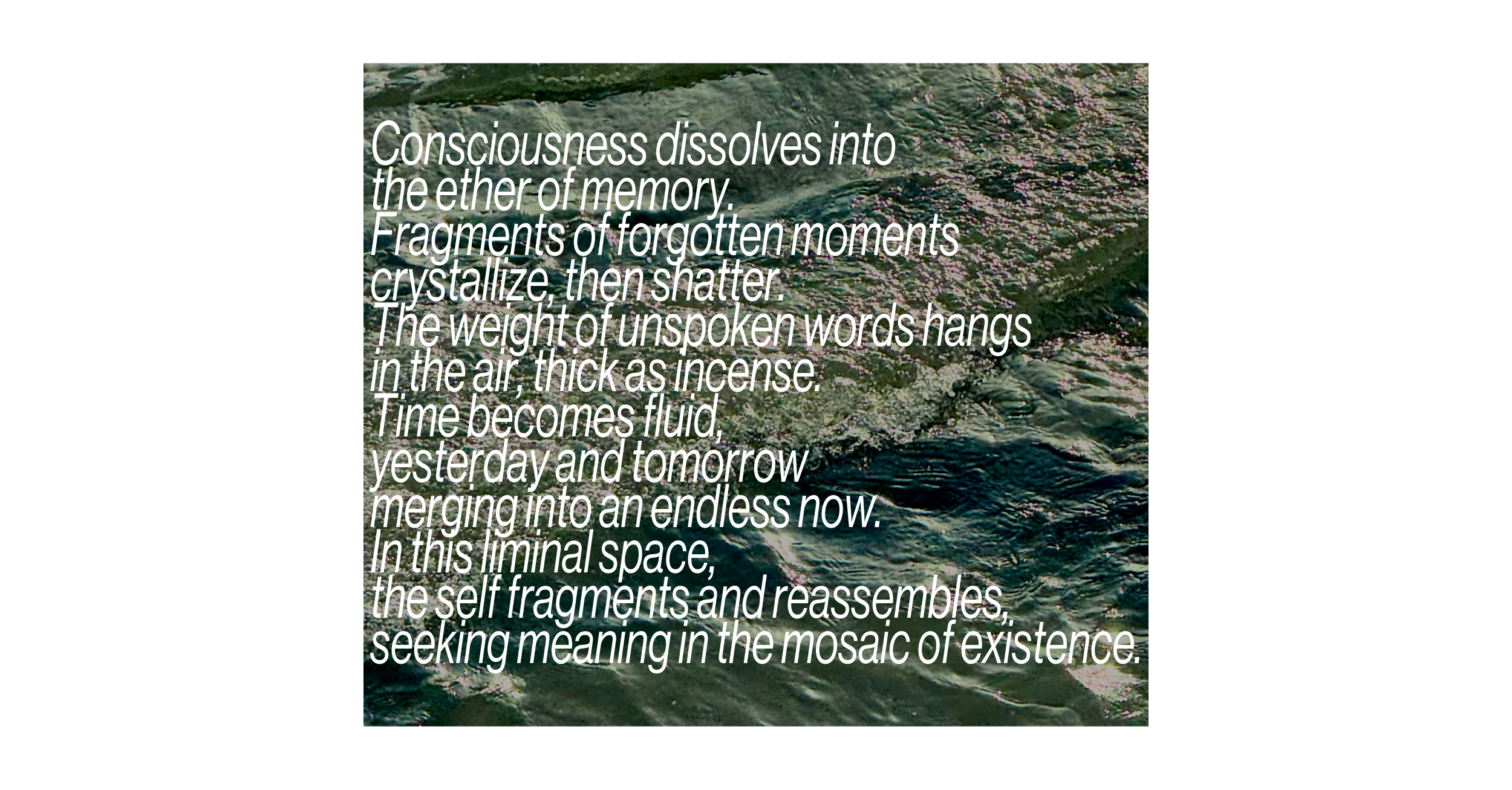ガヤガヤとしたテレビの音は、いつの間にか彼の選んだ穏やかな音楽に変わった。
ソファに並んで腰かけて、彼の匂いのする薄いTシャツに赤ワインがはねないように気をつけながら口をつけた。軽い口当たりなはずなのに薄らと裏側に苦さを感じて、なんだか今の私たちみたいな味だな、と笑いそうになってしまう。
「……ドヨン。」
「ん?」
「今日で最後に、出来ると思う?わたし。」
もう、終わりにするべきだと思った。これ以上進んでしまっては、きっとこの気持ちに名前が付いてしまうから。
「……何が?」
「なんでもない。できっこないから、忘れて。」
グラスを置いて、代わりに彼の手を取った。指先にキスするのが私たちの合図だった。
手首から手が絡め取られ、それからこれからのふたりを予行練習するみたいに指先がねちっこく交わる。よく切りそろえられた桃色の爪が私の青色のネイルと正反対なのにうつくしい。
そのまま首筋に顔を寄せる彼の髪を指で梳いた。耳の裏から鎖骨まで、余すところなく柔らかな唇が触れていく。
なにを必死に、と思うが、私たちには必要な儀式だった。
時折混ざる舌の感触に鼻腔から息が漏れる。
腰に腕が添えられて、穏やかに背をソファに預けた。
それまでの行為の柔和さとは裏腹の脚の間に手早く差し込まれた彼の膝が、Tシャツの隙間から腹を撫でる手が、隠せないおとこの性を表しているようで興奮する。
どこまで私に普段親切に振舞ったって、この男はおんなを蹂躙したくてたまらない欲望を抑えきれないのだ。その歪さが甘くてくせになった。
大切な特別だったらこの男はこんなふうに牙を剥かないだろうし、私も思うがままに振る舞えなかっただろう。
ある意味では嘘偽りのない関係だからこそ、快楽だけにひたむきになれた。
アダムとイヴが知恵の実を得る前のように、悦楽だけを享受したい。それだけだった。